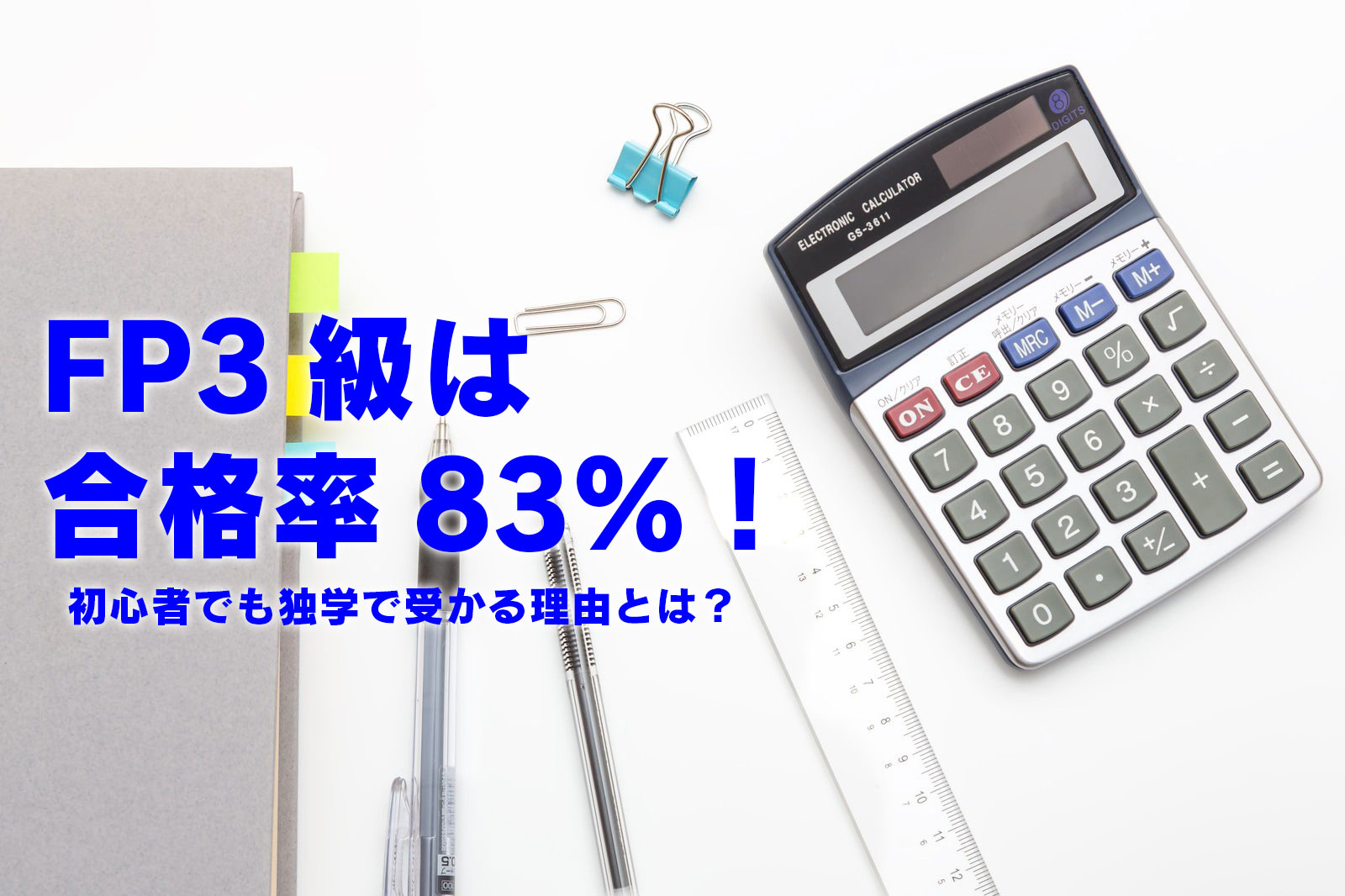「FP3級を受けてみたいけど、独学で合格できるのか不安…」
そんな方に向けて、この記事ではFP3級の最新合格率(2024年〜2025年)をもとに、独学でも合格できる理由をやさしく解説します。
さらに、試験団体による違いや合格しやすさのポイント、自分に合った勉強法の選び方、効率的なスケジュールの立て方など、これから学習を始める初心者に役立つ情報をまとめました。
仕事や家事・学業と両立しながらでも、正しい方法で取り組めばFP3級は十分に合格が狙える国家資格です。
この記事を読めば、「独学でやってみようかな」と前向きに思えるはずですよ。
▶ FP試験合格に向けて最初の一歩を踏み出すなら
スタディングFP2級・3級講座の詳細はこちら
【2024年最新】FP3級の合格率と受験団体の違いを徹底比較
FP3級の合格率は、他の国家資格と比べて比較的高めで、特に「初心者におすすめの資格」として人気があります。
ただし、実は試験を実施している団体(日本FP協会/きんざい)によって合格率や問題傾向が異なることをご存じでしょうか?
この記事では、2024年以降の最新合格率データをもとに、それぞれの団体の違いと受験の選び方をわかりやすく解説します。
最新の合格率データ(2024年以降)
まずは、直近の試験結果から、合格率を比較してみましょう。
初心者にとって試験の難易度をイメージする手がかりにもなります。
| 試験回 | 実施団体 | 学科 合格率 | 実技 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 日本FP協会 | 約85.8% | 約92.0%(資産設計提案業務) |
| 2024年1月 | きんざい | 約59.1% | 約59.3%(個人資産相談)/約52.8%(保険顧客資産相談) |
| 2023年9月 | 日本FP協会 | 約86.3% | 約90.6% |
| 2023年9月 | きんざい | 約60.0% | 約57.0% 前後 |
※合格率は年度・試験内容により変動します。最新情報は日本FP協会公式サイトまたはきんざい公式サイトでご確認ください。
日本FP協会の実技試験は合格率90%超と非常に高く、全体的に受かりやすい印象があります。
一方できんざいの実技は、受験者の多くが苦戦しており、やや難易度が高い傾向です。
FP協会ときんざいの違い|どちらで受けるべき?
結論として、はじめてFP試験を受ける初心者には、日本FP協会での受験がおすすめです。
その理由を詳しく見ていきましょう。
● 出題形式と難易度の違い
- 日本FP協会の実技(資産設計提案業務)は、図表や選択肢が多く「広く浅く」のスタイル。生活に役立つ知識が中心で、初心者にも理解しやすい構成です。
- きんざいの実技(個人資産相談/保険顧客資産相談)は、記述や文章理解が必要な設問が多く、実務に近いイメージ。特に金融・保険業界を志望する人向けです。
● 合格基準は共通だが、結果に差が出る
- 両団体とも学科・実技ともに6割以上正解で合格(絶対評価)です。
- ただし、問題の難易度や出題傾向の違いにより、合格率には最大30ポイント近い差が生まれています。
● 資格としての効力はどちらも同じ
- どちらで合格しても、「ファイナンシャル・プランニング技能士3級」の国家資格が取得できます。
- 履歴書やキャリア上の効力に違いはなく、どちらを選んでも資格としての価値は同じです。
📌 きんざいを選ぶのはこんな人におすすめ
「すでに保険や金融の現場で働いている」「より実務に即した内容で挑戦したい」という方には、きんざいの出題傾向が合っている場合もあります。
迷ったら、日本FP協会での受験が安心
特に「初めての資格試験」「勉強に不安がある」という方は、合格率の高い日本FP協会を選ぶことで、より自信を持って取り組めます。
受験日程や試験会場は、以下の公式サイトから確認できます:
FP3級は独学でも受かる?向いている人の共通点とは
FP3級は独学でも十分に合格可能な資格です。
ただし、すべての人に独学が向いているとは限りません。学習スタイルや生活環境によって、独学の「相性」が分かれるからです。
ここでは、独学のメリット・デメリットを整理し、実際に独学で合格した人たちの体験談をもとに、どんな人が独学に向いているのかを探っていきます。
📚 独学のメリット・デメリット
まずは、独学によるFP3級対策の特徴を、メリットとデメリットに分けて見ていきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 費用が安く済む(書籍代のみ) | モチベーション維持が難しい |
| 自分のペースで学べる | 理解に時間がかかる部分でつまずきやすい |
| 復習しやすく調整自由 | 勉強の順序や重要度が不明瞭になりがち |
| 無料の過去問サイトが豊富 | 疑問点をすぐに解消できないことがある |
👤 独学が向いている人の特徴
独学合格者の傾向を見ると、以下のような特徴を持つ人が多いです:
- コツコツと1人で学ぶのが苦にならない
- スケジュール管理がある程度できる
- ネットや書籍で調べるのが得意
- 過去に独学で資格取得の経験がある
❗ 通信講座を検討した方がよいタイプ
一方で、以下のような方には通信講座の方が合っているかもしれません:
- 忙しくて時間が限られている
- 計画を立てるのが苦手
- 何から始めればいいか分からない
- 教えてくれる人がいた方が安心できる
多く合格者が選んだ学習法を、あなたも試してみませんか?
スタディングFP3級・2級講座はこちら
🗣 独学合格者の体験談と傾向
SNSやブログでは、「FP3級 独学 合格体験談」として多くの投稿が見られます。
その中から、年代や立場による傾向が見えてきました。
🎓 20代学生
就活に役立つかもと思って独学で挑戦。テキストと問題集だけで1ヶ月半くらい。想像よりも身近な内容が多くて、楽しく勉強できました!
→ 学習習慣がある若年層は、短期集中で乗り切るタイプが多いです。
👩👧👦 主婦
子育てのスキマ時間にスマホで少しずつ。朝の30分と、子どもが寝た後の時間で2ヶ月。無料の過去問サイトが神。
→ スキマ時間を工夫して積み重ねる“継続型”の成功パターンが目立ちます。
👨💼 社会人(30〜40代)
仕事終わりに毎日30分、休日に2〜3時間。2ヶ月で合格できました。最初は難しそうだったけど、内容が生活に直結してて意外と面白い。
→ 平日と休日のバランス学習+生活への実用性がモチベーションになっているケースが多いです。
🧭 まとめ|独学で受かるかは「向き不向き」で決まる
独学合格は「勉強時間の確保」よりも、「やり方」と「継続の工夫」がポイントです。
あなた自身の性格や生活リズムに合わせて、無理なく続けられる方法を選ぶことが、合格への最短ルートになります。
FP3級は独学より通信講座?迷っている人が選んだ3つの理由
FP3級は独学でも合格できる国家資格ですが、「続けられるか不安」「何から始めればいいか分からない」と感じていませんか?
実は最近、通信講座を選ぶ人が増えているのには、明確な理由があります。
SNS(X、YouTube、Yahoo!知恵袋など)でも「独学で挫折したけど通信講座で合格できた」という声が多く、忙しい社会人や主婦、学生にとって、効率よく合格を目指せる選択肢として注目されています。
このセクションでは、実際に選ばれている理由を3つに絞って、リアルな体験談と私の経験も交えて紹介します。
FP3級 通信講座がスキマ時間に強い理由
FP3級の通信講座(特にスタディング)は、スマホ1つで学習できるように設計されています。
- 動画講義が短く、1本10〜15分で完結
- 通勤・育児・家事のスキマ時間にぴったり
- 自動マーカーや進捗管理機能で復習しやすい
「通勤中に講義を視聴→夜に問題演習」という流れが自然に続きました(30代・会社員/X投稿より)
忙しくても、毎日10分ずつの積み重ねで合格ラインに届く。
そんな“続けやすさ”が選ばれている理由のひとつです。
FP3級 通信講座は講師の解説でつまずきにくい
独学では「何が大事かわからない」「理解に時間がかかる」といった悩みがつきもの。
通信講座なら、専門講師による丁寧な解説で、学習のつまずきを最小限に抑えられます。
- 図解つきの講義で初心者でも理解しやすい
- テキスト→動画→問題演習の順番が明確
- 勉強の計画を自分で立てなくても進められる
「独学だと迷子になりがちだったけど、通信講座は道筋があるから安心して進められました」(40代・主婦/知恵袋より)
通信講座は、理解しやすさだけでなく、学習の習慣化までサポートしてくれるのが魅力です。
FP3級 通信講座を使ってみた感想|スタディングの実力は?
私もFP3級の勉強を始めるとき、「独学で頑張るか、通信講座を使うか」でかなり迷いました。
そこでスタディングの無料体験を試してみたところ、「これなら続けられそう」という手応えを感じました。
実際に使ってみて良かったところ
- スマホで完結するので、スキマ時間を有効活用できる
- 講義のテンポがちょうどよく、集中しやすい
- 苦手問題だけを集めて復習できる機能が便利
私は「動画+スマホ派」なので相性が良かったですが、「紙の本でじっくり読みたい」タイプの方には少し物足りないかもしれません。
ただ、無料で使える範囲でも十分に雰囲気がわかるので、まずは実際に触れて判断してみるのが一番確実です。
📌 迷っているなら、まずは無料体験で“続けられる感覚”を試してみてください。
合格への一歩が、きっとそこから始まります。
➡ [スタディングFP講座公式ページで無料体験 ▶]
FP3級は何時間で合格できる?初心者向け勉強時間と3ヶ月スケジュール例
FP3級を目指すうえで、最初に気になるのが「何時間くらい勉強すれば合格できるのか?」という疑問ではないでしょうか。
私自身も、勉強を始める前に「どのくらいの時間が必要なのか」「1日どれくらいやれば間に合うのか」が不安でした。
結論から言うと、FP3級の勉強時間の目安は約80〜150時間。
スケジュールさえ工夫すれば、1日30分でも3ヶ月で合格できる現実的な目標です。
このセクションでは、初心者・経験者それぞれの学習時間の違いと、私が実際に取り組んだ3ヶ月スケジュールの具体例をご紹介します。
初心者・経験者の勉強時間の違い
以下は、初心者と経験者それぞれのFP3級合格までの勉強時間の目安です。
生活スタイルや知識の有無に応じて、自分に近いタイプを参考にしてみてください。
| タイプ | 勉強時間の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初学者(知識ゼロ) | 約100〜150時間 | 全6分野を基礎から理解する必要あり。最初は用語に慣れることが重要。 |
| 経験者(簿記・保険・税金に触れている人) | 約60〜100時間 | 一部の分野は復習レベルでOK。アウトプット重視でも対応可能。 |
私も完全な初心者だったので、最初は用語が難しく感じて「本当に覚えられるのかな…」と不安でした。
でも、繰り返すうちに自然と慣れてきて、少しずつ知識がつながっていく感覚がありました。
1日30分で合格できる?3ヶ月スケジュール例を紹介
「毎日忙しくて、まとまった時間が取れない…」という方も多いと思います。
実際、私も1日30分前後の学習時間しか確保できない日がほとんどでした。
でも、1日30分×約90日=約135時間あれば、十分に合格ラインに届きます。
FP3級は「6割正解で合格」の絶対評価なので、毎日少しずつ進めるだけでも現実的な合格が狙える試験です。
🗓 FP3級|3ヶ月スケジュール例(平日30分+休日1時間)
| 期間 | 学習内容 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 1〜2週目 | テキスト通読(全体像を把握) | 理解よりも全体を“ざっくり”把握することを重視 |
| 3〜6週目 | 分野別にインプット+章末問題 | 過去問を解く土台を作る。苦手な用語にマーカーを引いておく |
| 7〜10週目 | 過去問演習と解き直し | 出題傾向に慣れる/間違えた原因をノートに書き出す |
| 11〜12週目 | 予想問題や模試で総仕上げ | 時間を測って解く練習/忘れていた知識を最終確認 |
💡 スケジュールをこなすコツ
- 平日は通勤時間・昼休み・就寝前を活用すると継続しやすいです
- 休日は午前中にまとめて学習すると、午後が自由に使えて気持ちも楽になります
- 学習記録アプリやカレンダーで進捗を“見える化”するとモチベーションも維持しやすくなります
私も最初は「こんなにやることが多いのか」と感じていましたが、完璧を目指すよりも“繰り返し”を重視したことで、知識が少しずつ定着していきました。
焦らず、でも毎日少しずつ進める。これが一番の近道です。
📌 FP3級の合格までの流れは、「学ぶ→解く→繰り返す」のシンプルなループです。
1日30分でも、自分のペースを保ちながら進めれば、確実に合格は見えてきます。

FP3級初心者が最短で合格する3ステップ勉強法
「FP3級、やってみよう!」と思った今が、学習スタートのベストタイミングです。
最後にご紹介するのは、私が初心者として実践し、効果を実感した3ステップの勉強法。
独学でも通信講座でも使えるこの方法なら、「何から始めればいいの?」という迷いもすぐに解消できます。
勉強の順序が決まるだけで、毎日の積み重ねがグッとラクになりますよ。
ステップ① テキストで全体像をつかむ
まず最初は、FP3級の全体像をざっくり把握することが大切です。
私はいきなり問題に取り組むのではなく、「6分野にどんな内容があるのか」「どこが得意・苦手になりそうか」を知るところから始めました。
私が使ったのは『みんなが欲しかった!FPの教科書(TAC出版)』。図解が豊富で読みやすく、初心者でも進めやすかったです。
最初の目的は、「完璧に理解すること」ではなく「全体の地図を描くこと」。
どこに何があるかが見えると、次のステップが迷いなく進められます。
ステップ② 問題集でアウトプットを重ねる
ステップ①で全体像をつかんだら、次は実際に手を動かして知識を定着させる段階です。
ここでは、問題集を使ってアウトプット中心の学習に切り替えます。
私が使ったのは『みんなが欲しかった!FPの問題集(TAC出版)』。
教科書とセットになっていて連動しやすく、解説も図解つきでとてもわかりやすかったです。
間違えた問題にマーカーをつけて、何度も繰り返すことで知識がしっかり定着しました。
最初は正解できないことも多かったですが、「なぜ間違えたか」を理解することで、記憶がどんどん定着していきました。
解けない=自分の伸びしろ。焦らず、淡々と積み重ねればOKです。
解説を“読むこと”も、れっきとしたインプットになります。
ステップ③ スマホでスキマ学習を習慣に
アウトプットのベースができてきたら、最後の仕上げはスキマ時間の活用です。
私は通勤時間やちょっとした待ち時間に、『FP3級ドットコム』やスタディングのアプリを使って○×クイズや一問一答を繰り返していました。
このステップで特に意識したのは、「スキマ時間=学習時間」として“習慣化”すること。
たとえば、朝のコーヒータイムに10分だけ問題を解く、アラームで通知をセットしておくなど、毎日同じタイミングに学習を紐づけることで、自然と勉強が生活に溶け込むようになりました。
スマホ1つで、1日15分の積み重ねが1ヶ月で7時間以上の差に。
「今日はまだアプリ開いてないな」と気づくようになれば、もうこっちのものです。
📌 まとめると、FP3級の最短合格に必要なのはこの3ステップ:
- テキストで全体像をつかむ(地図を描く)
- 問題集でアウトプットを重ねる(手を動かす)
- スマホでスキマ学習を習慣にする(毎日続ける)
完璧を目指すより、「昨日より1問でも覚える」気持ちで取り組めば、合格は十分に見えてきます。
私もこの流れで、無理なく合格することができました。
まとめ|FP3級は初心者にもやさしく、合格しやすい国家資格
FP3級は、お金に関する基礎知識が幅広く学べて、しかも初心者からでも十分に合格を狙える国家資格です。
実際に私も、全くの未経験からスタートして、テキスト+問題集+スキマ学習の3本柱で、ムリなく合格を目指すことができました。
これまでの記事でお伝えしてきたように、FP3級は:
- 合格率が高く(特に日本FP協会では90%前後)
- 出題形式もマークシート中心で取り組みやすく
- 生活に直結する内容で学びが実感しやすい
という、まさに“初めての資格チャレンジ”にぴったりの存在です。
もし今「独学でやれるか不安…」という気持ちがあるなら、まずはテキストを1ページだけ開いてみてください。
通信講座が気になる方は、無料体験から始めてみるのもおすすめです。
📌 大事なのは、一歩を踏み出すこと。
完璧を目指さなくても、少しずつ続けていけば、合格は確実に近づいてきます。
✅ 最後に、この記事でお伝えした「初心者が合格するまでの道のり」をもう一度まとめておきます。
- 合格率の違いを知って、自分に合う受験方式を選ぶ
- 独学 or 通信講座、自分に合う学び方を見つける
- 勉強時間とスケジュールを可視化して、習慣化する
- テキスト → 問題集 → スマホ学習 の3ステップで知識を定着させる
FP3級は、「自信がない」「忙しい」「何から始めたらいいかわからない」そんな人にこそおすすめしたい資格です。
さあ、次はあなたの番です。
今日から少しずつ、自分のお金の知識と未来を、アップデートしていきましょう!
▶ 学び始めるのに、最適なタイミングは”今日”です。
スタディングFP3級・2級講座はこちら