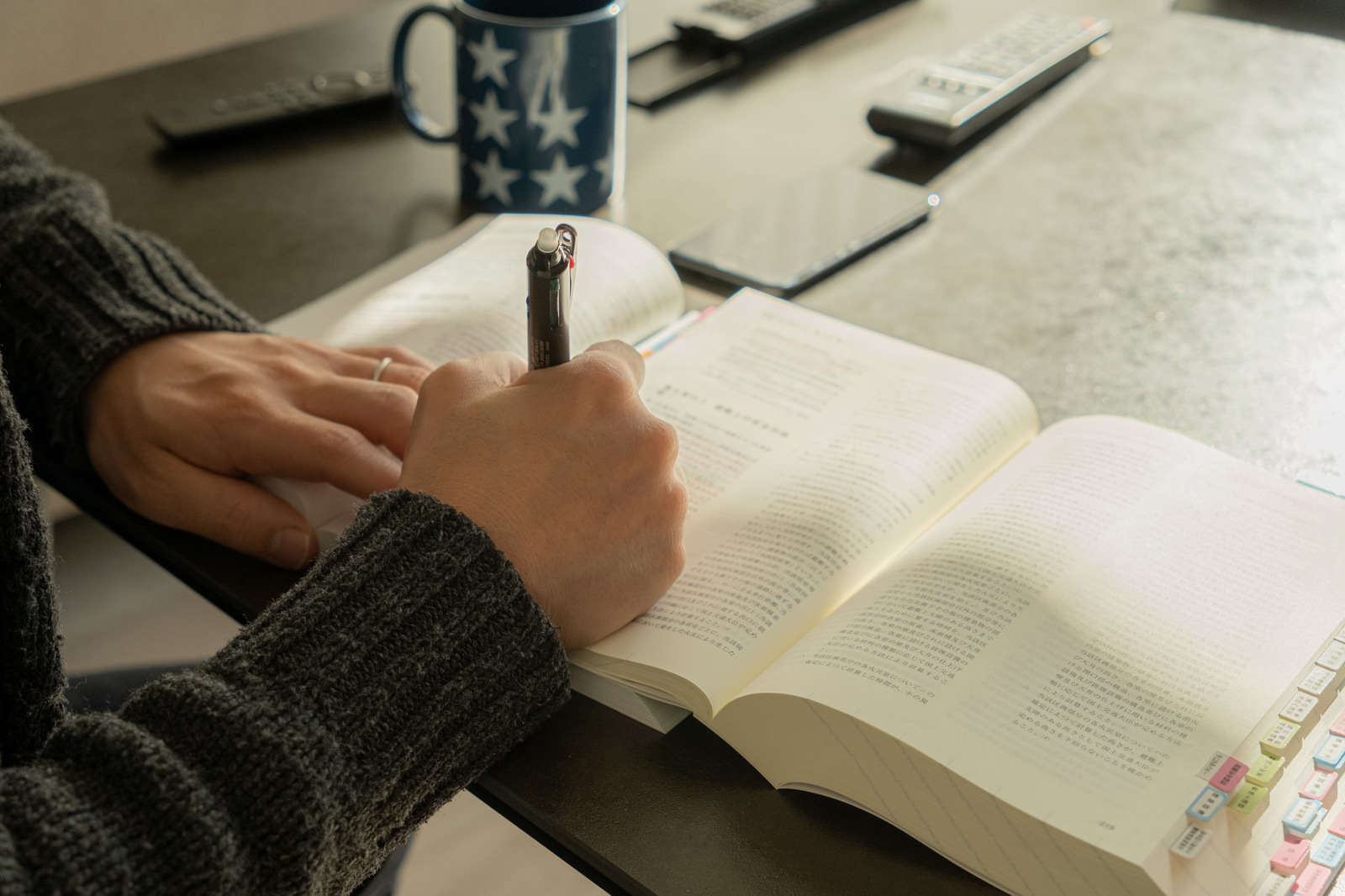宅建試験の独学合格を目指していると、必ずぶつかる疑問があります。
「過去問っていつから始めればいいの?」
「何年分を、何周すれば合格できるの?」
「ただ解くだけじゃ意味ないって聞くけど、どう進めればいい?」
そんなあなたに、独学合格者の学習法を徹底調査してまとめた過去問演習の進め方を、スケジュール例や具体的なコツとともにお伝えします。
【Q&A】宅建過去問はいつから始める?
Q. 宅建の過去問演習はいつから始めればいい?
A. テキスト学習と並行して始めるのが最も効率的です。
**理由:**インプットした知識をすぐにアウトプットすることで、理解が深まり記憶にも定着しやすくなるからです。
**補足:**最低でも試験3か月前には、本格的に過去問演習をスタートしましょう。
宅建過去問演習を始めるベストタイミング
「テキストを一周してから過去問」と考える人も多いですが、実際にはインプットとアウトプットを並行する方が効率的。
こんなスケジュールをイメージしてください。
| 月 | 学習内容 | 目安時間/日 |
|---|---|---|
| 4月〜6月 | テキストメイン+過去問試し解き | 1〜2h |
| 7月〜9月 | 過去問中心の演習+弱点補強 | 2〜3h |
| 10月 | 模試・総仕上げ | 2〜3h |
4月〜6月は、テキストを読み進めつつ、章末やテーマごとに過去問を解くことで知識が定着します。7月以降は過去問をメインに据え、試験本番で得点できる実力を育てていきましょう。
過去問演習の具体的な進め方
① まずは全体を1回解く
最初から完璧を目指す必要はありません。
**目的:**問題の傾向や出題分野を把握すること。
- 目安時間:1問2〜3分 × 50問=約2.5時間
解けなくても落ち込む必要はありません。「今は傾向をつかむ時期」と割り切りましょう。
② 間違えた箇所をテキストで復習
ここが合格者と不合格者の分かれ道。
- 間違えた問題は解説を読むだけでなく、必ずテキストに戻って知識を補強してください。
- 目安時間:1問あたり5分(解き直し+テキスト確認)
知識の“穴”を一つずつ埋める作業が、得点力アップにつながります。
③ 分野別→年度別で繰り返す
過去問演習は、ただ年度別に解くだけでは不十分です。
- 5年分×3周以上が合格者の王道パターン
- 最初は分野別で知識を整理 → その後、年度別で本試験形式に慣れる
1周あたりの目安日数は10〜14日程度。繰り返すことで、解法パターンが体に染み込みます。
よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 解ける問題だけ解きがち | 全問解き直し、苦手克服こそ得点UPの鍵 |
| 古い問題集を使う | 法改正に対応できない。最新版を購入する |
| 解説を読まず答え合わせだけ | 必ず「なぜその答えになるのか」を理解する |
おすすめの宅建過去問集と選び方
比較表|出版社・特徴・価格帯・学習スタイル
| 出版社 | 特徴 | 価格帯 | 学習スタイル |
|---|---|---|---|
| TAC | 分野別・解説詳しい | 約2,500円 | 紙派 |
| LEC | 頻出問題に絞られている | 約2,000円 | 紙派 |
| ユーキャン | 初学者向け解説が丁寧 | 約2,500円 | 紙派 |
| スタケン | スマホで演習・アプリ対応 | 月額1,000円前後 | アプリ派 |
✅ **ポイント:**分野別編で知識整理→年度別編で総仕上げが王道です。
宅建過去問出題傾向(分野別出題率)
出題率イメージ
- 権利関係:30%
- 宅建業法:20%
- 法令上の制限:20%
- その他(税・免除科目など):30%
出題割合を意識すると、過去問演習の優先順位が明確になります。
合格者の声|過去問演習で変わった瞬間
📌 ケース① 年度別→分野別切り替えで得点UP
「6か月独学。TACの分野別過去問集でインプット180h、アウトプット120h。本試験34点で合格!」
📌 ケース② 解くだけ学習から解説熟読へ
「3か月独学。LECの過去問集を使い、インプット90h、アウトプット110h。本試験36点で合格。」
▶ 使用教材レビューはこちら
まとめ|過去問演習を合格への武器に
宅建合格には、過去問演習が最重要です。
インプットとアウトプットを並行し、間違えた問題をテキストで補強しながら繰り返す。
これを徹底するだけで、合格率は大きく上がります。
✅ もし「効率よく勉強を進めたい」「忙しくてまとまった時間が取れない」と感じているなら、
スタディングの宅建講座を使うのも一つの方法です。
- スマホだけでスキマ時間に講義+過去問演習ができる
- 学習管理機能で進捗が一目瞭然
- 通学よりも圧倒的にコスパが良い
👉 [スタディング宅建講座の詳細はこちら]