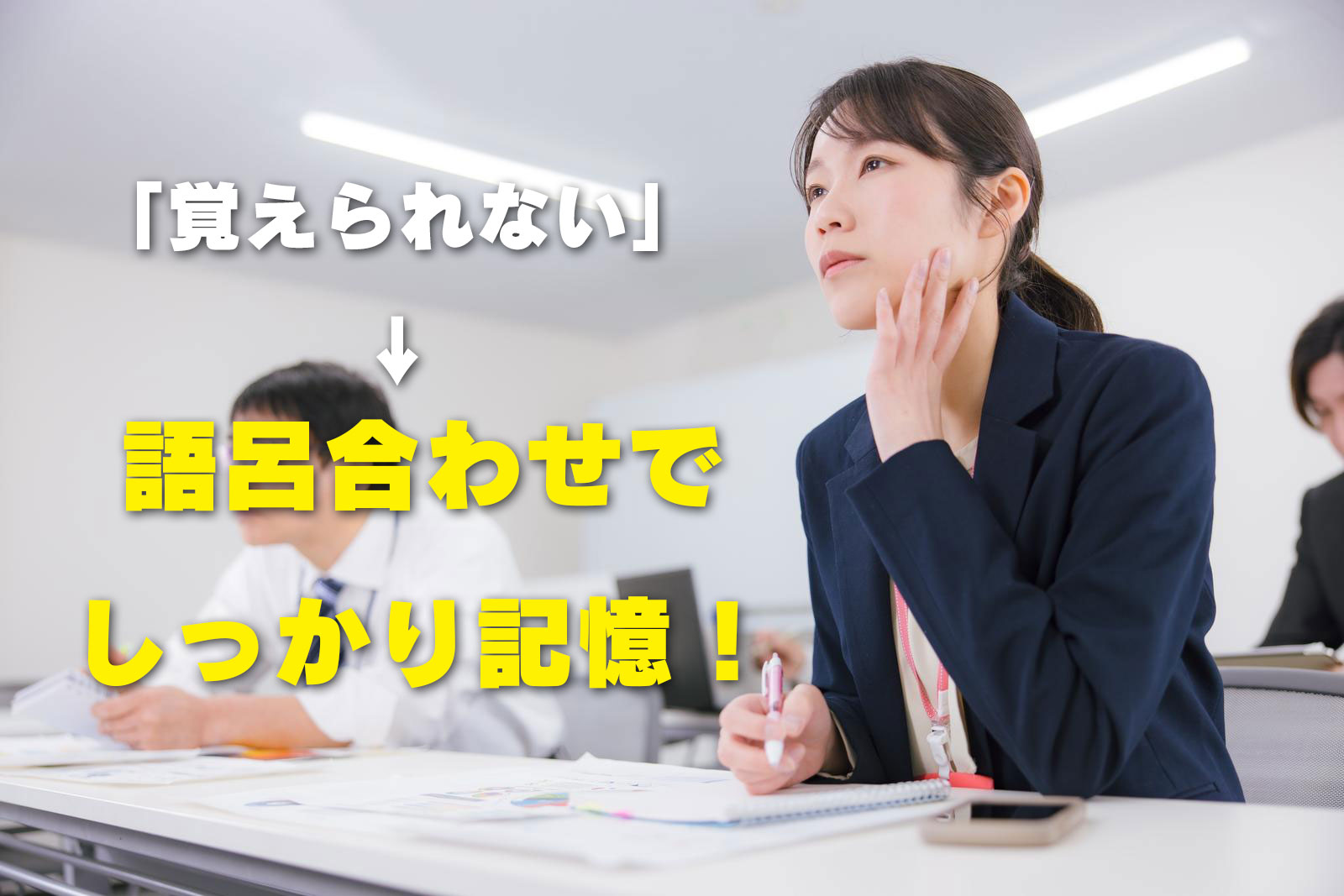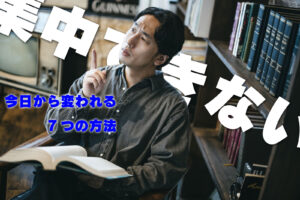「また忘れた…」「何回覚えても頭に残らない…」
資格試験の勉強中、こんなつぶやきをしたことはありませんか?FP3級や簿記、宅建などを独学で進めていると、専門用語や数字が多すぎて、覚えたそばから抜け落ちてしまう感覚に陥ることがあります。
私自身もFP3級の勉強を始めたばかりの頃、例えば「生命保険料控除の限度額」や「退職所得の税率区分」など、数字や制度の羅列に頭がパンクしそうでした。そんなときに出会ったのが「語呂合わせ」です。
語呂合わせは、ただのダジャレ…と思ったら大間違い。
実は教育心理学の分野でも効果が認められているれっきとした“記憶術”で、「リズム」「感情」「連想」などを通じて、短期記憶から長期記憶への橋渡しをしてくれるのです。東京大学の学習支援センターでも、語呂合わせは効果的な暗記法として紹介されていますし、多くの資格受験生が実際に活用しています。
この記事では、「語呂合わせはなぜ覚えやすいのか?」という根拠から、FP・簿記・宅建など資格ごとの語呂実例、さらに誰でも今日から使える語呂の作り方のコツまで、暗記が苦手な人でもすぐ実践できる方法を紹介していきます。
暗記が苦手でも大丈夫。語呂合わせは、あなたの記憶力を劇的に変える“最強の武器”になります。
今日から、暗記のストレスにさよならして、“覚える楽しさ”を手に入れましょう。
語呂合わせはなぜ資格試験に効果的?
語呂合わせは、単なる語感遊びやダジャレではありません。
記憶に残りにくい数字や抽象語を“意味のある情報”に変換し、脳がスムーズに処理・保存できる状態へ導いてくれる強力なツールです。実際に、教育心理学や認知科学の研究でも、「連想」「リズム」「感情」「ストーリー」が記憶の定着を助けるとされています。
ここでは、語呂合わせがなぜ資格試験の勉強に効果的なのかを、脳の働き・心理的メカニズムの視点から解説します。
リズム・感情・ストーリーが記憶定着を強化する理由
人間の脳は、意味のない情報を単独で記憶するのが苦手です。
一方で、感情を伴う言葉やリズミカルな表現、ストーリー仕立ての情報には強く反応し、長期記憶に定着しやすい傾向があります(Baddeleyのマルチコンポーネントモデルでも示唆されています)。
語呂合わせはこの点において非常に優れており、「かしわもち(仮登記・処分制限・本登記・地上権)」のように、可愛らしい響きとリズムで印象に残しやすくなっています。さらに、語呂にちょっとしたオチや感情的なインパクトがあると、記憶がより強化されることが心理学の研究でも確認されています。
つまり、語呂合わせは“感情×音のパターン×文脈”という、記憶定着の三拍子を自然に備えた記憶術なのです。
語呂合わせ以外にも、脳科学に基づいた暗記法はたくさんあります。
👉 ストーリー法で記憶力アップ!勉強が楽しくなる覚え方
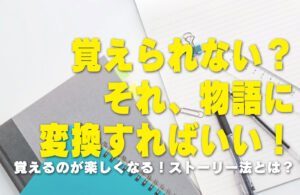
意味のない情報が「意味づけ」されることで覚えやすくなる
資格試験では、数字・税率・用語の分類など、一見すると「意味がない」「つながりがない」情報が大量に登場します。こうした情報はワーキングメモリ(作業記憶)では処理しきれず、長期記憶に残すのが難しいという問題があります。
ここで力を発揮するのが語呂合わせです。
語呂を使えば、断片的な知識にストーリー性や比喩的な意味づけを与えることができ、脳の“意味ネットワーク”にスムーズに取り込まれます(semantic network theory)。
たとえば「いっときのゴリラ、得した50万」なんていう語呂を聞くと、一時所得の特別控除50万円という内容が、頭の中に面白いイメージごと保存されるのです。
この「意味づけ」のプロセスこそが、語呂合わせの本質であり、記憶効率を何倍にも高める鍵となります。
語呂合わせは、手続き記憶やエピソード記憶にも作用する
語呂合わせが優れているのは、単なる“記号の置き換え”ではなく、体験として記憶に残る点にあります。たとえば何度も声に出して唱えるうちに、自然と語呂のフレーズが体に染み込んでいく──これは手続き記憶(procedural memory)の領域に近い現象です。
また、自分で語呂を考えたり、勉強仲間と笑いながら語呂を共有したりした記憶は、エピソード記憶(episodic memory)として保存され、試験直前の追い込みでも意外なほどスッと引き出すことができます。
つまり、語呂合わせは「知識を記憶する」だけでなく、「記憶に残る行動・感情体験」を作り出す点でも非常に優秀なのです。
あなたも、自分だけの語呂合わせをひとつ作ってみませんか?
「覚えられない」が「忘れない!」に変わる第一歩になるかもしれません。

語呂合わせの使いどころ|資格勉強で活きる場面とは
実際にどんなときに語呂合わせが役立つかを具体例で紹介。
語呂合わせは、資格試験のあらゆる分野で活躍する“万能ツール”です。
特に、用語の羅列・数字の分類・制度の種類など、頭で整理しづらい項目ほど語呂の効果が抜群に発揮されます。ここでは、FP3級・簿記・宅建という代表的な資格試験を例に、語呂合わせがどう活かせるのかを具体的に紹介していきます。
FP3級の暗記項目に強くなる
不動産、年金、税制などの語呂実例と活用方法
FP3級の語呂合わせは、資格試験の暗記法として非常に有効です。
6つの出題分野にわたって膨大な知識を覚える必要がありますが、その中でも特に語呂合わせが効果的なのが「不動産」「公的年金」「税制」の3ジャンルです。
不動産登記の優先順位を覚えるには、
「かしわもち」= 仮登記 → 処分制限の登記 → 本登記 → 地上権
という語呂が有名です。“食べ物”のイメージで親しみやすく、音のリズムも良いため、順番が自然に定着しやすくなります。
※登記の優先順位は実際の法律上、事案によって異なる場合があります。この語呂は試験対策としての整理法として活用されています。
年金では、
「こくみんコックり年金」= 国民年金・厚生年金・国民年金基金・確定拠出年金
という語呂がよく知られています。制度名が似ていて混乱しやすい分野でも、音の特徴でグループ分けができる点がメリットです。
また、税制分野では数字が頻出ですが、
「いっときのゴリラ、得した50万」= 一時所得には50万円の特別控除
といったユニークな語呂にすると、視覚的・感情的なイメージが湧き、印象に残りやすくなります。
FP3級の出題範囲全体の攻略ポイントも押さえておくと安心です。
👉 FP3級の出題範囲をやさしく解説|6分野の特徴と勉強ポイント

簿記で出てくる数字や勘定科目に対応
簿記の勉強では、勘定科目の分類や仕訳ルールの暗記が大きなハードルになります。
「資産」「負債」「費用」「収益」など、似た言葉が並ぶうえに、借方・貸方の増減関係を正確に押さえる必要があるからです。
そんなときに役立つのが、以下のような語呂です。
あさひるね、ふかけつしゅうしゅう
- 資産・費用・繰越利益剰余金 → 借方が増える
- 負債・資本・収益 → 貸方が増える
対比構造が語呂に組み込まれているため、視覚的にも整理しやすくなっています。
※あくまで仕訳の意味理解と併用する補助的な記憶法です。
さらに、数字を扱う場面でも語呂は効果的です。
よく知られているのが「いっせんえん、にーまるまる(1000円=200円)」というフレーズ。
一見すると「1,000円の契約書でも200円の印紙が必要」と誤解しそうですが、実務上は 1万円未満の課税文書には印紙は不要(非課税) です。
ではなぜこの語呂が使われるのかというと、「印紙税は200円から始まる」という最低ラインを覚えるための工夫だからです。
実際には、1万円以上〜100万円以下の課税文書で200円、それ以上は金額に応じて400円、1,000円…と段階的に増えていきます。
すべての金額表を丸暗記するのは大変ですが、「200円スタート」と覚えておけば、試験中に細かい数字で迷わず判断しやすくなるのです。
つまりこの語呂は、**厳密な金額表そのものではなく、試験対策の“記憶のきっかけ”**にすぎません。
実務では必ず最新の税法や国税庁の資料を確認する必要がありますが、学習段階では「印紙税=200円からスタート」と押さえることで、混乱を避けやすくなります。
宅建は語呂天国?重要事項の暗記効率化
宅建業法や法令制限など、語呂で整理すべき分野を紹介
宅建は、法律用語・数字・義務や罰則の違いなど、細かい知識を正確に覚えることが求められる試験です。そのため、語呂合わせとの相性が非常に良いのが特徴です。
たとえば宅建業法では:
- 「こやつ、とほうで、こうしん」= 5つの免許取消事由
→ 営業停止命令違反、公正取引違反、法令違反、供託所違反、更新申請拒否
言葉にリズムがあり、イメージしやすいため、複雑な法律用語を“人の行動”のように捉えて覚えられます。
※実際の条文との照合や根拠条文の確認とあわせて使用すると、理解が深まります。
法令上の制限では:
- 「ちょっと いってくる」= 都市計画区域 → 準都市計画区域 → 市街化調整区域 → 特定用途制限区域 → その他
→ 抽象的な用語の順序を“移動の流れ”のようにたとえることで、記憶の手がかりになります。
宅建のように出題範囲が広く、類似概念が多い試験では、語呂で**“分類”と“流れ”を記憶する**のが得点アップの鍵となります。
語呂合わせは“ただの暗記法”ではなく、“資格試験を攻略する戦略”にもなります。
まずは、自分の苦手分野から語呂を探してみましょう。覚える楽しさが、勉強のモチベーションにもつながります。
※語呂合わせは記憶の補助として活用し、制度や条文の理解とセットで取り入れるのがおすすめです。
語呂合わせを作る7つのコツ|誰でも作れる記憶術
「覚える」だけじゃもったいない。
語呂合わせは、自分で“作れるようになる”と記憶力がぐんと伸びます。
ここでは、FPや簿記・宅建などの資格試験で役立つ語呂を、自分で作るための具体的なコツを7つ紹介します。
ちょっとした工夫で、あなたの脳に刺さる“オーダーメイド暗記法”が完成します。
せっかく作った語呂も、勉強が続かなければ活用できません。習慣化の工夫もセットで取り入れてみましょう。
👉 資格勉強が続かない人必見!3日坊主を卒業する方法
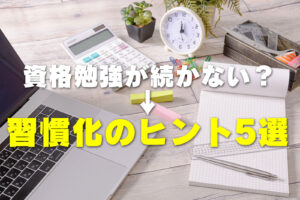
数字語呂の作り方|変換表付きで初心者も安心
数字系の用語や制度は、語呂で処理できると記憶効率が一気に上がります。
そのためには「数字をどう読み変えるか」という基本ルールを押さえておくことが重要です。
たとえば「1=い/ひと」「2=に/ふ」「3=さ/み」といったように、数字を音に変換していきます。
| 数字 | 読み方の例 |
|---|---|
| 1 | いち、ひと |
| 2 | に、ふた |
| 3 | さ、みっつ |
| 4 | よん、し |
| 5 | ご、いつつ |
| 6 | ろく、む |
| 7 | なな、しち |
| 8 | はち、や |
| 9 | きゅう、く |
| 0 | れい、まる |
複数の音を使い分けられるようになると、語呂の自由度が一気に広がります。
数字が多い簿記や税制の暗記にも効果抜群です。
感情に刺さる語呂の作り方|笑える・驚ける・忘れない
語呂合わせは、ちょっと笑える・おかしい・ツッコミたくなるほど記憶に残ります。
それは脳が“感情とセットの情報”を優先的に保存する性質を持っているからです。
たとえば
「いっときのゴリラ、得した50万」=一時所得の特別控除50万円
という語呂は、意味が多少雑でもイメージが強烈なため忘れにくいですよね。
正確性より「印象優先」。ちょっとふざけたくらいの方が、むしろ効果的です。
ストーリー型語呂で覚える!記憶に残る語呂の構成法
ストーリー仕立ての語呂は、エピソード記憶として脳に刻まれます。
覚えにくい概念も「出来事」として語れば、まるでドラマのワンシーンのように再生できるのです。
例:
「タケシは宅建の更新忘れて免許取り消し」
→ 宅建業法の免許取消事由を“人物の失敗エピソード”として記憶。
「誰が」「何をして」「どうなった」だけで、記憶のストーリーラインが完成します。
リズムで覚える語呂のコツ|音読で記憶が定着する理由
語呂は目で読むより、耳と口を使ってリズムで覚える方が圧倒的に定着します。
音に出すことで「ワーキングメモリ→手続き記憶」へスムーズに変換されるからです。
たとえば
「ちょっと いってくる」=都市計画区域の分類
のような日常フレーズ調の語呂は、口に出すたびに脳内で再生されやすくなります。
声に出してテンポ良く。語呂は「読む」ではなく「歌う」くらいがちょうどいいんです。
意味不明でもOK!無理やり語呂が記憶に残る理由
語呂は“意味が通じること”より、“なんか気になる”ことの方が大事。
実際、変な語呂ほど記憶に残ります。
たとえば
「ごろごろ寝てるのに、不動産3つ」
→ ご=仮登記、ろ=処分制限、ね=本登記…とあとから意味を当てはめる形でもOK。
脳は異常値やノイズに敏感です。
最初は無理やりでも、後で意味をくっつければ記憶は強化されます。
推し×語呂の覚え方|好きなものに絡めるだけで定着UP
好きなもの・推し・趣味のキャラと結びつけると、語呂は爆発的に覚えやすくなります。
脳が「自分に関係ある」と認識することで、エピソード記憶+感情記憶が合体するからです。
例:
「FP=Fateポイント」「宅建=タケシ検定」
→ 勉強が“自分ごと”になると、暗記が苦じゃなくなります。
「誰にも見せないから大丈夫」。恥ずかしい語呂ほど効果アリです。
語感で決まる!覚えやすい語呂の特徴と語尾の工夫
語呂の記憶効果は「意味」より「語感」によって決まることが多いです。
リズム・音の切れ味・語尾のまとまりが良いと、脳がフレーズとして記憶しやすくなります。
例:
「ふかけつしゅうしゅう」=貸方が増えるもの(負債・資本・収益)
→ 音の繰り返しとテンポが良く、口に出して気持ちいい。
覚えやすい語呂の特徴は「短い・軽い・語尾が締まる」の3拍子です。
語呂合わせは、“作っているとき”こそが一番覚えている瞬間。
今日覚えたいワードがあるなら、自分専用の語呂を一つ作ってみましょう!
今すぐ使える!資格試験の語呂合わせ実例集
FP・簿記・宅建の分野別に、すぐ活用できる語呂を厳選紹介。
語呂は“使うだけ”で記憶が加速する。
作れなくても、使いこなせば合格に近づける。
ここでは、FP3級・簿記・宅建それぞれの試験でよく出る分野に特化した、実際に使える語呂合わせの例を厳選してご紹介します。
どれも多くの受験者が使ってきたものばかり。
「これ、覚えづらかったやつ!」と思ったら、ぜひ使ってみてください。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 語呂だけでなく、効率的に知識を整理するなら通信講座も活用したいところ。
スタディングなら要点を動画とテキストで繰り返し学べるので、語呂と合わせて知識を定着させやすくなります。
👉 スタディング公式サイトで詳細を見る
━━━━━━━━━━━━━━
FP3級で役立つ語呂まとめ
ライフプランニングと資金計画
「こうけんろういか」
→ 健康保険、厚生年金、労災、雇用、医療、介護
→ 社会保険制度の種類をリズムよく分類。語尾の「いか」は“医療・介護”の略で語感も自然
リスク管理
「火災じしん、そんがい保険」
→ 火災保険、地震保険、損害保険
→ 短くまとめると、似た種類の保険を混同しにくい
金融資産運用
「かぶしんたくふどうさい」
→ 株式、信託、不動産、債券
→ 投資商品の主要カテゴリーを端的に整理できる
タックスプランニング
「いっときのゴリラ、得した50万」
→ 一時所得には50万円の特別控除
→ 感情インパクト+数字の組み合わせが秀逸
※「ゴリラ」に意味はありませんが、語感のインパクトで数字が記憶に残る好例です
不動産
「かしわもち」
→ 仮登記、処分制限の登記、本登記、地上権
→ リズム+親しみやすさが記憶をサポート
※実際の優先順位は状況により異なるため、試験対策用の整理法として使用
相続・事業承継
「はいこまごふぼそきょう」
→ 配偶者・子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹
→ 相続の順位と範囲をリズムで整理。視覚的な並びに注意
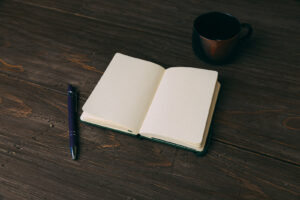
簿記で役立つ語呂まとめ
借方・貸方の増減ルール
「あさひるね/ふかけつしゅうしゅう」
→ 借方が増える:資産・費用・繰越利益剰余金
→ 貸方が増える:負債・資本・収益
→ 分類が反復語呂になっていてテンポも良好
仕訳の方向混同防止
「さかふひしょ」「ふしかしし」
→ 借方4文字/貸方4文字
→ 意味より音で流れを覚える構造
数字関連の定番語呂
「いっせんえん にーまるまる」
→ 1,000円の収入印紙=200円
→ テンポが良く、試験中に頭で再生しやすい
勘定科目の対比整理
「しさんでひようをつかって、もうけはしゅうしゅうする」
→ 資産・費用=使う側、収益・資本=得る側
→ 意味+動作でイメージでき、簿記初心者の混乱解消に効果的
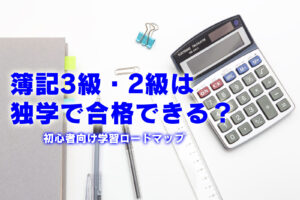
宅建で役立つ語呂まとめ
宅建業法:免許取消事由
「こやつ、とほうで、こうしん」
→ 営業停止命令違反、公正取引違反、法令違反、供託所違反、更新申請拒否
→ フレーズ調で語呂にテンポがあり、5項目を一括記憶しやすい
※条文との照合推奨(宅建業法第13条など)
法令上の制限:用途地域の分類
「ちょっと いってくる」
→ 都市計画区域 → 準都市計画区域 → 市街化調整区域 → 特定用途制限区域
→ 「移動をイメージさせる語呂」で順番の理解がスムーズに
建築基準法:建築確認が不要なケース
「ぞうかいいってんじゅう」
→ 増築・改築・移転・10㎡以下・用途変更なし
→ 条件が多く混乱しやすいため、リズムで押さえると◎
重要事項説明書に記載する項目
「じゅうしょようせつ」
→ 売主の氏名・所在地、用途地域、接道状況など
→ 語感よりも頭文字による整理が記憶に有効

自分の苦手分野に“語呂の武器”を投入するだけで、記憶の引き出しが格段に増えます。 まずは1つ、すぐに使える語呂を試してみましょう!
語呂合わせの落とし穴とは?記憶を“知識”に変える3ステップ
語呂合わせは、記憶の“入口”をつくる強力なツールです。けれど、使い方を間違えると、せっかく覚えた知識が試験本番で“出口不明”になることも──。
特に資格試験のように、知識の正確さや応用力が問われる場面では、語呂の扱い方ひとつで結果が大きく変わってきます。
ここでは、語呂合わせを効果的に使うために押さえておきたい注意点と、やってしまいがちな落とし穴について解説します。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 語呂は記憶の“入口”。意味理解と演習が欠かせません。
スタディングはテキスト→演習→復習が自動化されているので、語呂をきっかけに知識へつなげやすい仕組みになっています。
👉 スタディング公式サイトで詳細を見る
━━━━━━━━━━━━━━
❶ 意味が分からなければ応用できない
語呂合わせで知識を思い出す“きっかけ”をつくるのは効果的ですが、試験で問われるのはあくまで意味や仕組みの理解です。
たとえば、「いっときのゴリラ、得した50万」という語呂で“一時所得の特別控除”を覚えていたとしても、「なぜ特別控除があるのか」「給与や退職金とどう違うのか」といった応用問題には対応できません。
語呂は「思い出すきっかけ」にすぎません。
語呂で記憶の引き出しを開いたら、必ずテキストや講義内容で中身を確認する、という意識を忘れずに。そうすることで、暗記が知識に進化します。
❷ 語呂が多すぎると逆に混乱する
「すべて語呂で覚えよう!」と意気込んで、あらゆる用語に語呂をあてはめると、かえって混乱のもとになることがあります。
とくに似たような語感の語呂が増えてくると、「これって何の項目だったっけ?」と迷ってしまい、試験本番で混乱することも。
語呂合わせは、苦手な部分や覚えづらい数字・分類など、ポイントを絞って使うのがベスト。
全体を語呂で固めるのではなく、「理解をメインに、語呂は補助輪」として使うイメージで活用しましょう。
❸ 語呂→意味理解→出力の順で使う
人は「すでに知っていること」にしか新しい知識を結びつけることができません。
この“すでに知っていること”の枠組みを、認知心理学では「スキーマ」と呼びます。
スキーマは、知識を整理する“棚”や“引き出し”のようなもの。
語呂合わせは、その棚に「ラベルを貼る作業」として機能します。
正しい学習の流れは、以下の3ステップです:
- 語呂でスキーマ(記憶の引き出し)をつくる
- テキストで意味・背景を理解する
- 問題演習で繰り返し出力して定着させる
たとえば宅建受験者向けの語呂「こやつ、とほうで、こうしん」は、宅建試験の「免許の拒否事由」に関する語呂です。それぞれが何を指しているかをテキストや条文と照らし合わせて理解します。
- こ:営業停止命令違反
- や:公正取引違反
- つ:法令違反
- と:供託所違反
- ほう:法律違反(重複チェック)
- こうしん:免許更新申請の拒否
語呂で“型”をつくり、意味を理解し、演習で使ってみる。この順序を意識することで、記憶が“自分の知識”に変わります。
語呂合わせは、記憶の“入口”をつくる優れたツールです。でも、それをゴールにしてしまっては不十分。
語呂でスキーマを作り、意味で中身を補い、演習で知識に仕上げる。
この3ステップを意識することで、記憶が定着しやすくなり、合格への道がぐっと近づきます。
まとめ|語呂合わせは資格試験対策の“味方”
━━━━━━━━━━━━━━
📌 暗記に苦労する人でも、効率的な学習環境があれば合格は十分可能です。
スタディングならスマホでスキマ時間に学習でき、語呂+反復演習で記憶を強化できます。
👉 スタディング公式サイトで詳細を見る
━━━━━━━━━━━━━━
語呂合わせは、「覚えられない」を「忘れない」に変えるための心強い味方です。
特に、数字や抽象語が多い資格試験においては、記憶の“入口”をつくる強力なツールとして機能します。
ただし、それだけでは合格に届きません。
大切なのは、語呂を“きっかけ”にして、意味を理解し、繰り返し演習していくこと。
語呂→意味理解→出力という3ステップを意識することで、単なる暗記が“使える知識”へと進化していきます。
語呂合わせは、数ある記憶術の中でも特に実用性の高い手法です。
うまく活用すれば、あなたの学習効率は飛躍的に向上します。
「どうせ覚えられない」とあきらめる前に、まずはひとつ、あなたに合った語呂を見つけてみましょう。
今日からきっと、勉強がちょっと楽しくなるはずです。