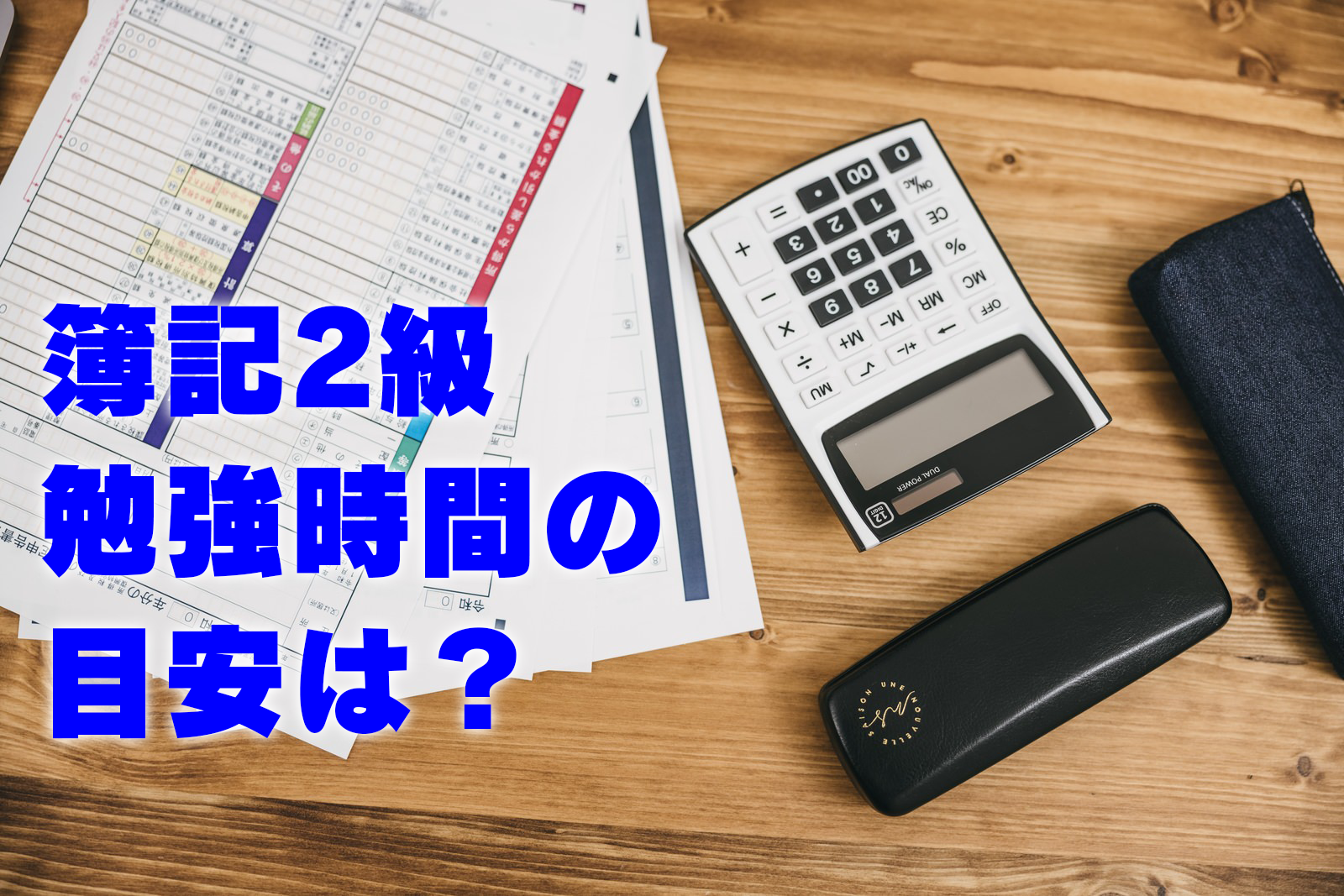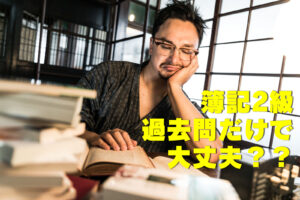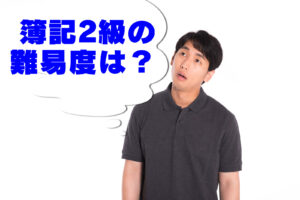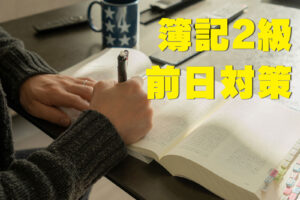簿記2級は独学で合格できるのか、そして勉強時間はどれくらい必要なのか──。
資格取得を目指す多くの人が最初に気になるポイントです。
忙しい社会人や学生にとって、限られた時間の中で効率よく学習を進めるためには、目安となる勉強時間と、時間を短縮する工夫を知ることが欠かせません。
この記事では、独学と講座利用の勉強時間の違い、合格者のデータをもとにした現実的な目安、そして最短ルートで合格を目指すための短縮テクニックをわかりやすく解説します。
簿記2級の勉強時間は独学と講座でどのくらい違う?
簿記2級に合格するために必要な勉強時間は、独学か講座利用か、さらに簿記3級の経験があるかどうかによって大きく変わります。
独学はどうしても遠回りが多く時間がかかりがちですが、講座を活用すれば効率的に短縮できます。
ここでは、勉強時間の目安から実際の合格者データ、さらに短縮の理由までまとめて解説します。
簿記2級の独学・講座・経験別の勉強時間の目安
簿記2級の勉強時間は、学習方法や背景知識によって大きく変わります。
- 独学:250〜350時間
- 講座利用:150〜250時間
- 簿記3級済み/経理経験あり:100〜150時間
平均すると独学で300時間前後、講座で200時間前後が一つのラインです。
ここから条件に応じて短縮できるイメージを持つと現実的です。
簿記2級の勉強が「独学よりも講座」で100時間以上短縮できる根拠とは?
簿記2級に合格するための勉強は、独学よりも講座を受講した方が効率的です。
なぜ講座を使うと100時間以上短縮できるのか、その根拠を具体的に解説します。
予備校や通信講座が示す簿記2級の勉強時間
大手予備校や通信講座(TAC、大原、クレアール、スタディングなど)が公開している「想定学習時間」を比較すると、
- 独学(市販教材を中心とした場合):250〜350時間
- 講座利用(動画や問題演習がセットになった場合):150〜250時間
この差からも、講座を利用すれば100時間以上の短縮が十分に現実的であることがわかります。
合格者データに見る簿記2級の学習時間の傾向
実際に合格した人たちの学習時間を集めてみると、独学組はおおよそ300時間前後、講座組は200時間前後という傾向が見られます。
こうしたデータからも、講座を利用することで100時間以上短縮できることが裏付けられています。
講座を使うと簿記2級の勉強時間が短縮できる理由
独学と講座では、学習の効率に大きな違いがあります。
無駄な遠回りが減る分、講座なら100時間以上の学習時間を削減できるのです。
| 学習スタイル | 特徴 | 結果 |
|---|---|---|
| 独学 | 教材選びに時間がかかる 理解のために調べ直しが必要 学習順序を試行錯誤する必要あり | ロスが多く、学習時間が増えやすい |
| 講座 | 出題頻度に応じた効率的な学習順序が組まれている 講師の解説で理解が速い インプットと演習が一体化している | 無駄が少なく、100時間以上短縮が可能 |
━━━━━━━━━━━━━━
📌 忙しい社会人でも簿記2級合格を狙うなら、効率的な学習環境づくりがカギ。
スタディングならスキマ時間を習慣化でき、無理なく試験日まで走り切れます。
👉 今すぐスタディングの簿記講座をチェックする(公式サイト)
━━━━━━━━━━━━━━
あなたが簿記2級に合格するための「最短時間」を見積もる方法
自分の場合に必要な勉強時間を見積もるには、ベース時間から調整するのが分かりやすいです。
1. ベース時間を選ぶ
| 学習タイプ | 時間の目安 |
|---|---|
| 初学 × 独学 | 300時間 |
| 初学 × 講座 | 200時間 |
2. 短縮条件を引く
| 条件 | 短縮時間 |
|---|---|
| 簿記3級合格済 | ▲70時間 |
| 経理経験あり | ▲60時間 |
| 数学・会計に抵抗がない | ▲20時間 |
| 学習管理が得意 | ▲20時間 |
3. 生活制約を足す
| 条件 | 増加時間 |
|---|---|
| 週2日以下しか学習できない | +30時間 |
| 学習ブランクが長い | +20時間 |
例えば、講座を利用して200時間をベースに、簿記3級合格済(▲70)、経理経験あり(▲60)、ただし学習ブランクが長い(+20)の場合、合計で約90時間。
実際には100〜150時間を目安に考えると安全です。
👉 スタディングなら進捗管理を自動化して、独学より効率的に学習を進められます(公式サイト)
簿記2級の出題傾向と学習配分|独学効率化の設計図
簿記2級は「商業簿記」と「工業簿記」の2つで構成されています。
それぞれの比率や勉強の配分を押さえておくことが、効率的に合格するための第一歩です。
商業簿記と工業簿記の出題比率
簿記2級の試験は、商業簿記が約60%、工業簿記が約40%を占めます。
商業簿記では仕訳や決算整理、固定資産や有価証券といった論点が中心。
一方の工業簿記は、原価計算や総合原価・個別原価、CVP分析などが頻出です。
この比率を意識して、勉強時間を振り分けることが効率化の第一歩となります。
効率的な学習配分の目安
勉強の配分は次のバランスを意識すると効果的です。
- インプット(講義・テキスト):30%
- 演習(問題・過去問):60%
- 総復習(模試・弱点潰し):10%
インプットに偏りすぎず、演習の比重をしっかり取ることで、得点につながりやすくなります。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 出題傾向に合わせた効率的なカリキュラムで学びたい人は、講座を活用するのもおすすめです。
👉 スタディング簿記講座の詳細はこちら(公式サイト)
━━━━━━━━━━━━━━
短サイクルで回す学習が効率的
同じ論点を長時間まとめてやるよりも、「短サイクル×多回転」で繰り返す方が定着が速くなります。
1日15〜30分でも小分けに復習する方が、脳の記憶定着システムに合っており、結果的に学習効率が高まります。
このリズムを意識して勉強計画を立てることが、最短合格への近道です。
簿記2級の学習モデル|1〜3か月で合格を目指す
簿記2級は必要な勉強時間が150〜300時間と幅広いので、自分の生活リズムに合った計画を立てることが重要です。
1か月で一気に仕上げたい人もいれば、2〜3か月でじっくり進めたい人もいます
ここでは勉強時間に応じて「1か月集中型」「2か月標準型」「3か月余裕型」の3モデルを紹介します。
自分に最も合ったプランをイメージしながら読んでみてください。
1か月集中モデル(120〜150時間)
簿記3級を持っている、週末に時間が取れる、講義を倍速で消化できる人に向いています。
インプットは10日以内に圧縮し、残りは演習に集中します。
毎日3〜5時間の学習時間をキープできれば、1か月での合格も可能です。
2か月標準モデル(180〜220時間)
初学者でも現実的に取り組みやすい王道プランです。
平日は1日2時間、土日は6時間前後を目安に学習時間を組み立てると、インプットと演習のバランスを取りながら着実に進められます。
このペースなら、2か月で180〜220時間に到達し、合格に必要な基礎力と得点力を無理なく積み上げられます。
3か月余裕モデル(220〜300時間)
完全な初学者や、平日は1時間程度しか取れない人に向いています。
復習サイクルに余裕を持たせられるため、知識の定着度は高くなります。
合格までの道のりは長くなりますが、安定感のある学習計画です。
👉 スケジュール設計が不安な人は、スタディングの学習プランを参考にしてみてください(公式サイト)
簿記2級に独学で最短合格するための勉強法
簿記2級は学習範囲が広く、ただ時間をかければいいと言うわけではありません。
合格する人とそうでない人の差は「勉強の質」と「工夫」にあります。
最短で合格を目指すなら、インプットとアウトプットのバランス、誤答への向き合い方、工業簿記の攻略法などを戦略的に組み立てることが必要です。
ここからは、合格者に共通する勉強法のエッセンスを整理して解説します。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 独学でも合格は可能ですが、講義と演習を一体化できる講座を使えば、理解と得点化が加速します。
👉 今すぐスタディング簿記講座をチェックする(公式サイト)
━━━━━━━━━━━━━━
全体像は「広く速く」つかむ
簿記2級の勉強を始めたら、まずは細かい部分にこだわらず、全体像を素早く押さえることが大切です。
細部で立ち止まってしまうと全体の位置づけが見えにくくなり、効率が落ちます。
講義を一通り聞いたら章末問題を数問だけ解き、正誤を記録して翌日に確認する。
この繰り返しで、理解度7割でもいいから前へ進むことが、最短合格への鉄則です。
演習主導で「出題パターン」を体得する
簿記2級は出題傾向がはっきりしているので、効率よく合格するには演習を中心に据えるのが効果的です。
得点力は“パターン”のストック数で決まります。
例えば仕訳や決算整理、原価計算の基礎といった頻出テーマは、1日20〜30問ずつ小分けにして反復練習するのがおすすめです。
迷ったらまずは手を動かし、出題パターンを体に覚えさせることが近道です。
ミスの「理由」を10秒で言語化する
演習で間違えたときは、そのままにせず原因を短く言語化する習慣をつけましょう。
数字の計算ミス、用語の混同、手順の抜けなど、原因をはっきり分けることで対策が変わります。
例えば「計算順序の取り違え」とメモして付箋に残し、翌日に再確認する。
こうした誤答ノートは、最短合格に向けた強力な武器になります。
工業簿記は「図と表」で理解する
工業簿記を文章で理解しようとすると時間がかかりがちですが、図や表を使うと一気にスピードアップできます。
材料→仕掛→製品という原価の流れを図で描く。
CVP分析をグラフ化するなど、視覚で整理すれば短時間で理解が深まります。
計算式はあとから自然についてくるので、まずは図で覚えることを意識しましょう。
仕訳は「毎日10分」の習慣にする
仕訳は勉強量よりも頻度がものを言う分野です。
筋トレのように、短時間でも毎日継続することで定着します。
朝の10分を使い、仕訳を音読し、実際に書き、言葉で言い換える。
この小さな習慣が積み重なり、大きな成果につながります。
簿記2級を最短で合格するには、この“日課化”が欠かせません。
目指せ簿記2級独学合格!忙しい人の「時間の作り方」
簿記2級を学びたいと思っても、仕事や家事、学校で時間が限られている人は多いでしょう。
しかし、勉強時間は工夫次第で必ず作れます。
ここでは、忙しい人でも続けられる具体的な時間の確保術を紹介します。
👉 スキマ時間を習慣化しやすいスタディングは、忙しい社会人や学生に人気です(公式サイト)
通勤や昼休み、就寝前に10分枠を固定する
まとまった時間がなくても、通勤や昼休み、就寝前の10分は学習に活用できます。
この短い時間は暗記や仕訳の確認にぴったりで、細切れでも積み上げれば大きな成果につながります。
特に寝る前の復習は、睡眠中の記憶定着効果も期待できます。
講義は1.25〜1.5倍速で時短する
講義動画は通常速度で再生すると長く感じ、集中が続きにくいものです。
再生速度を1.25〜1.5倍に設定すれば、理解を損なわず効率よく学習を進められます。
慣れれば短時間で多くの内容を消化でき、限られた時間を有効に活用できます。
平日の誤答を週末に30分で復習する
平日に解いた問題で間違えた箇所を、そのままにしておくと弱点が残ります。
週末に30分まとめて誤答だけを振り返ると、効率的に穴を埋められます。
「誤答ノート」や付箋にメモしておけば、復習もスムーズに行えます。
カレンダーに「簿記枠」の時間を予め確保しておく
学習を「空いた時間でやる」と考えていると、つい後回しになりがちです。
予定表に「簿記学習」の時間をあらかじめブロックすることで、学習を生活の一部として固定できます。
スマホの通知機能を使えば、忘れることなく習慣化しやすくなります。
1日の学習ログを3行で記録する
今日やったことを簡単に3行で残すだけでも、学習の可視化につながります。
「仕訳を20問解いた」「工業簿記の講義を1本見た」など、短くても十分です。
振り返りができることで達成感が得られ、モチベーションの維持に直結します。
簿記2級のよくある遠回りと回避策
簿記2級の勉強では、効率を下げてしまう“やりがちな落とし穴”があります。
ここでは代表的な5つのケースを取り上げ、それぞれの回避策をまとめました。
参考書を増やしすぎない
複数のテキストに手を出すと、どれも中途半端になってしまいます。
合格レベルに到達するには、基本書1冊と演習書1冊を軸に回すだけで十分です。
新しい参考書が必要か迷ったら、その内容が過去問や演習書で十分にカバーされているかを確認してから購入を検討しましょう。
最短合格を目指すなら、参考書は増やすよりも「1冊を繰り返す」ことに集中する方が効果的です。
ノートを作り込みすぎない
ノートは“きれいにまとめる”よりも、“思い出すために書く”ことが重要です。
理解用ノートを丁寧に作っても、テキストの焼き直しにすぎず、記憶の定着にはつながりません。
時間ばかりかかって演習量が減るのは本末転倒です。
人は「すでに知っていること」に関連する情報しか覚えられないため、繰り返し思い出す行為こそが記憶のトリガーになります。
動画学習なら20分ごと、テキストなら章ごとに「今覚えていること」を3つだけ殴り書きする“記憶用ノート”がおすすめです。
箇条書きや短文で十分で、すべてを網羅する必要はありません。
思い出すこと自体が長期記憶への変換を促します。
残すべきは「誤答の原因」だけでOKです。
「なぜ間違えたか」を一行メモにしておけば、復習に直結します。
最短合格を目指すなら、ノートは“記録”ではなく“記憶の起点”として使いましょう。
きれいにまとめるよりも、間違いの理由を残す方が合格への近道になります。
過去問を最後まで取っておかない
「知識がついてから過去問に挑戦しよう」と考える人は多いですが、それでは演習のタイミングが遅れてしまいます。
過去問は2周目の学習から取り入れるのがおすすめです。
本番形式の問題に早く慣れることで、出題パターンをつかみ、効率的に得点力を伸ばすことができます。
合格を最短で狙うなら、過去問は“仕上げの道具”ではなく“学習の中心”として活用しましょう。
工業簿記を後回しにしない
工業簿記は馴染みが薄く苦手意識を持ちやすいため、つい商業簿記ばかりに時間を割いてしまいがちです。
しかし、工業簿記は試験全体の40%を占める重要分野です。
得点源にできれば合格が一気に近づきます。
苦手意識を放置すると大きな失点につながるため、毎週必ず1日は工業簿記に取り組むと決めておくと安定します。
バランスよく学習することで、苦手が減り、合格ラインを超える確率が高まります。
苦手論点を放置しない
不得意な論点を放置すると、本番で必ず失点に直結します。
間違えた問題には「計算ミス」「公式暗記不足」などのように原因を短い言葉でメモして、翌日に必ず復習する仕組みを取り入れましょう。
これを繰り返すだけで弱点は着実に潰せます。
最短合格を狙うなら「弱点を可視化し、次の日に潰す」ことを徹底するのがポイントです。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 独学で遠回りしがちなポイントも、講座なら最初から効率化された学習設計で進められます。
👉 効率的に学べるスタディング簿記講座の詳細はこちら(公式サイト)
━━━━━━━━━━━━━━
簿記2級の試験直前1〜2週間の過ごし方
試験直前の1〜2週間は、新しい知識を増やすよりも「これまでの力を本番で発揮できる状態に仕上げる」ことが大切です。
ここでは得点力を伸ばしつつ、不安を減らすための直前対策を紹介します。
👉 直前期はスタディングの模試機能を活用するのも効果的です(公式サイト)
本試験と同じ時間配分で練習する
本番では時間内にすべてを解き切るのが大きな課題になります。
そのため、直前期は商業簿記45分、工業簿記45分といった実際の配分で演習を繰り返しましょう。
時間の感覚を体に染み込ませることで、本番でも焦らず落ち着いて取り組めます。
頻出テーマだけを繰り返す
直前に新しい論点へ手を広げるのは効率が悪く、かえって不安を増やします。
この時期は、過去問で毎回出ている仕訳や決算整理、工業簿記の原価計算など、頻出テーマに絞って繰り返すのが効果的です。
よく出る問題を確実に取れるようにしておくことが、合格点への一番の近道です。
計算は途中点を意識して書く練習をする
簿記の試験は途中点が加点されるため、答えが合わなくても途中までの計算過程を残せば得点できます。
普段から「どの手順までなら点がもらえるか」を意識し、途中式を丁寧に残す練習をしておきましょう。
これに慣れておくと、本番での失点を大幅に防げます。
睡眠を優先して記憶の定着を促す
試験直前こそ、夜遅くまで勉強してしまいがちです。
しかし、知識の定着は睡眠中に行われるため、睡眠時間を削るのは逆効果です。
いつも通りのリズムで眠り、試験当日に頭が冴えている状態をつくることを最優先にしましょう。
模試は本番通りの時間で取り組み、時間感覚を養う
模試を解くときは「本番と同じ時間・同じ環境」で取り組むことが大切です。
実際に90分で解く練習をしておくことで、集中力の持続や時間配分の感覚を事前に掴めます。
本番さながらのシミュレーションを繰り返すことで、安心感が増し、当日の緊張も和らぎます。
まとめ|“最短合格”は設計できる
簿記2級の勉強時間は、条件が整えば最短100〜150時間での合格が可能です。
平均的には独学で250〜350時間、講座を利用して150〜250時間が目安となります。
ただし、重要なのは時間の多さではなく「効率の良さ」と「継続のしやすさ」です。
最短合格に近づくためのポイントは3つあります。
- 全体像を速くつかみ、勉強の全体像を見失わないこと。
- 演習中心で出題パターンを体得し、得点力を磨くこと。
- 誤答の原因を短くメモして翌日に潰すことで、弱点を放置しないこと。
これらを意識して学習を設計すれば、限られた時間でも合格点に到達するのは十分に可能です。
今日の10分が、数か月後の合格通知につながります。
あなたの生活に合った学習ペースで、簿記2級合格への道を歩み始めましょう。
━━━━━━━━━━━━━━
📌 独学に自信がない人も、効率的に合格を狙いたい人も。
スタディングならスマホでスキマ時間を活用できます。
👉 スタディング簿記講座の詳細はこちら(公式サイト)
━━━━━━━━━━━━━━