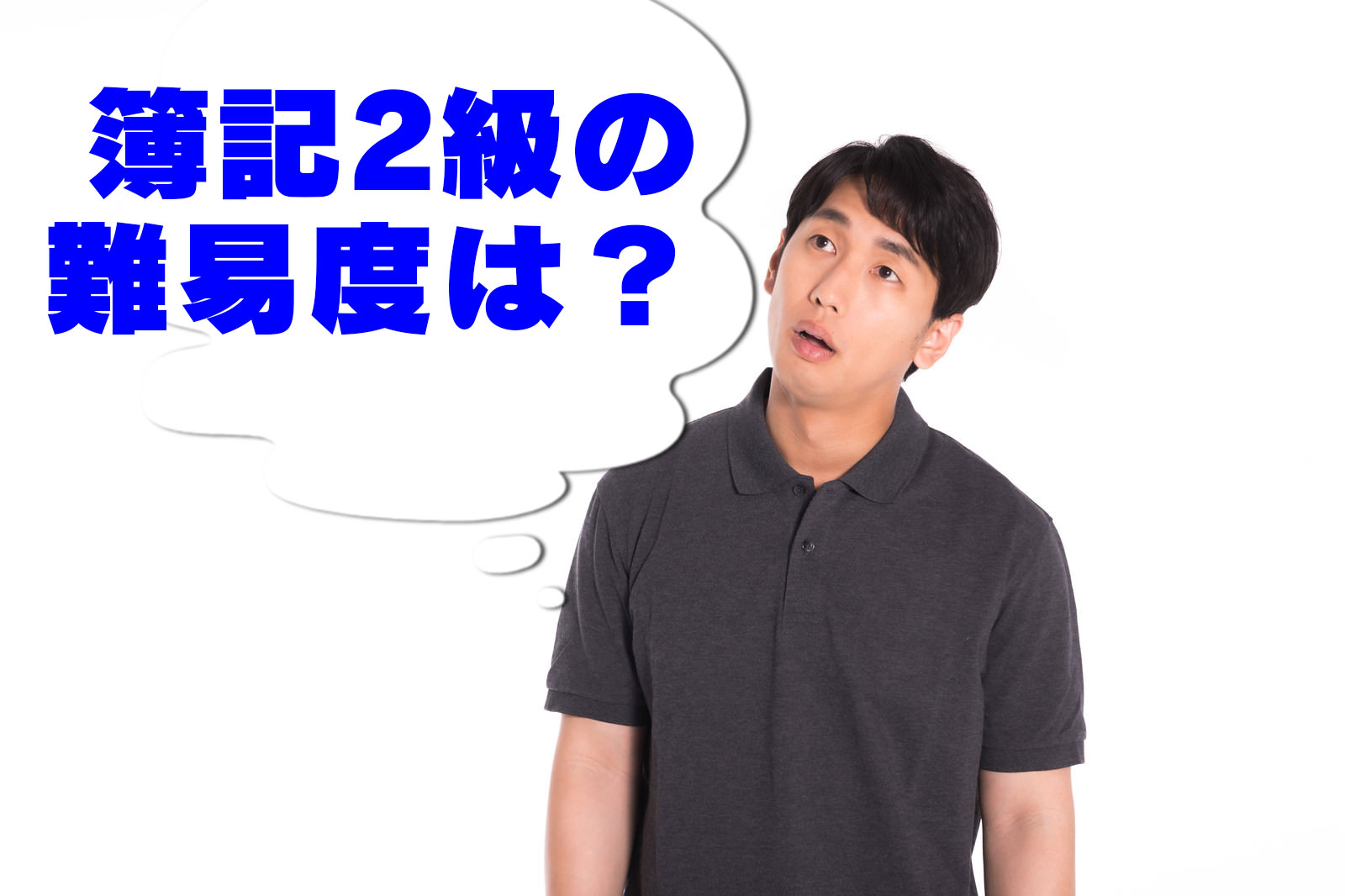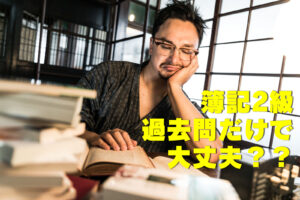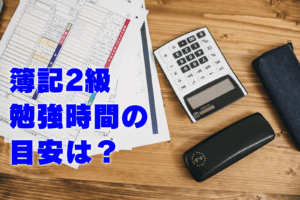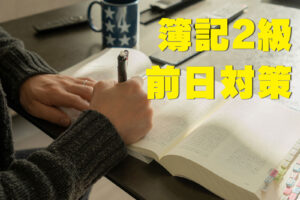「簿記2級は昔より難しくなったらしい…」
これから受験しようと考える多くの人が、そんな声を耳にして不安を抱えています。
確かに出題範囲の改定によって、簿記2級は従来より難化しました。
特に連結会計の追加は大きなインパクトで、「1級寄りの内容が降りてきた」とも言われます。
しかし、安心してください。
難しくなったのは事実ですが、適切な勉強時間と学習法を押さえれば十分に独学合格が可能です。
本記事では、簿記2級の最新の難易度を客観的なデータや比較を交えて解説し、難しくなった試験を独学で突破するための具体的な勉強法まで紹介します。
「難しくなった2級を最短で突破したい」「独学で挫折したくない」と感じた方は、
スキマ時間を活用できるスタディングの簿記講座をチェックしてみてください。
簿記2級は本当に難しい?合格率から見た難易度
難易度に関する議論を客観的に裏付けるため、まずは直近5年間の合格率推移を見てみましょう。
データが示す、簿記2級の本当のレベル感がわかります。
過去5年の合格率推移から見える難易度の変化
ここ5年間の簿記2級の合格率は15〜30%前後を推移しています。
年によってバラつきはあるものの、平均すると約20%程度に落ち着いています。
かつては30〜40%程度だった時期もありましたが、出題範囲の改定後は安定して低めの水準になっています。
この数字からも、制度変更前と比べると確かに「難しくなった」と言えるでしょう。
簿記3級との合格率比較で感じるレベル差
簿記3級の合格率がおおむね40〜50%前後であるのに対し、2級は20%前後。
この数字からも、簿記2級は3級の倍以上難しい資格と考えられます。
多くの受験生は3級合格後に2級に挑戦しますが、「一段階上がる」というより一気に山が高くなる感覚を持つ人が多いのはそのためです。
合格率だけでは測れない「学習負担の増加」
ただし、合格率の数字だけで難易度を判断するのは危険です。
簿記2級は、学習範囲が広がり「深さ」も増しているため、合格に至るまでに必要な勉強時間や理解度が大幅に増加しています。
つまり、「数字的な合格率」+「体感的な学習負担」の両面から、難易度が上がっていることは間違いありません。
簿記2級が「難しくなった」と言われる本質的な3つの理由
簿記2級が「難しくなった」と受験生に感じさせる背景には、明確な理由があります。
単に合格率が下がっただけでなく、出題範囲の改定が難化の核心です。
特に受験生がつまずきやすい3つの大きな要因を掘り下げて解説します。
特に難易度が急上昇!連結会計の追加と出題ウェイトの増大
2016年度の出題区分改定で、従来は1級レベルだった連結会計の一部が2級に追加されました。
子会社株式の取得や資本連結、債権債務の相殺消去といった論点は、初学者にはとてもハードルが高い分野です。
これにより、単純な仕訳の暗記だけでは太刀打ちできなくなり、理解力と応用力が強く求められるようになりました。
工業簿記で「理解の深さ」が求められるようになった
簿記2級は「商業簿記+工業簿記」の二本立てですが、近年は工業簿記の必須化と出題の難度上昇によって、「仕組みを理解して計算を組み立てる力」がなければ得点できません。
特に「製造間接費の配賦」や「標準原価計算」など、苦手意識を持ちやすい分野が合否を分けています。
実務家を意識した論点(収益認識・税効果会計など)の追加で暗記量が増加
会計基準の改正に合わせて、実務寄りのテーマが取り入れられるようになりました。
収益認識や税効果会計など、単純なパターン暗記では解けない問題が増えています。
その結果、従来より暗記量が増えたうえに、理解が浅いと解けないという二重の難化が起きています。
独学に限界を感じたら、通信講座を選ぶのも賢い手段ですよ。
👉 スタディング簿記級講座の詳細を見る(公式サイト)
簿記2級の難易度を他資格と比較するとどうか
簿記2級が「難しい」と言っても、他の資格と比べてどうなのか気になる方も多いはずです。
ここでは代表的な資格と比較してみましょう。
FP2級との比較|出題範囲の広さ vs 計算量の多さ
FP2級は幅広い知識を求められますが、計算問題はそれほど多くありません。
一方、簿記2級は「計算力・処理力」が圧倒的に重要です。
知識の暗記で突破しやすいFP2級に比べると、簿記2級の方が時間をかけた演習練習が必要になります。
宅建との比較|暗記中心 vs 理解+計算中心
宅建は法律や不動産知識の暗記が中心ですが、簿記2級は「理解+計算」のバランス型。
暗記が得意な人は宅建の方が合っているかもしれませんが、数字や論理的思考が得意な人は簿記2級に適性があります。
簿記1級との比較|2級はまだ“到達可能な現実ライン”
簿記1級は合格率10%以下、勉強時間1,000時間以上とも言われる超難関資格です。
それに比べ、簿記2級は初学者でも300〜400時間程度で現実的に合格を狙えるラインです。
「就職や転職に役立つ」「経理・会計の基礎固め」という意味でも、2級はちょうど良い目標といえます。
独学合格に必要な勉強時間・スキルと具体的な対策
簿記2級は難しくなりましたが、独学で十分合格可能です。
ここでは、合格に必要な勉強時間とスキル、そして具体的な勉強法を整理します。
簿記2級は難しくなったとはいえ、独学で十分合格可能です。
ここでは、合格に必要な勉強時間とスキル、具体的な勉強法を整理します。(→挫折しないためのより詳しい科学的勉強法はこちら)
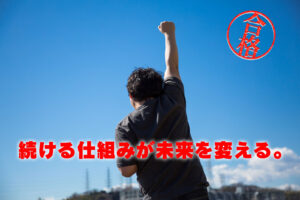
初学者は300〜400時間が目安|挫折しないための時間の作り方
簿記2級合格のための勉強時間は、初学者で300〜400時間が目安です。
1日2時間の勉強なら約5〜6か月、1日1時間なら約10か月かかります。
「忙しくて時間が取れない」という方は、通勤や家事の合間をスキマ時間に充てる工夫が合格のカギです。
『そんなに時間が取れない』と不安を感じた方もいるでしょう。スキマ時間を徹底活用できるスタディングなら、この勉強時間を大幅に圧縮することも可能です。
👉 スタディング簿記級講座の詳細を見る(公式サイト)
数字や計算が苦手でも克服できる?簿記特有の「パズル思考」
簿記の仕訳や原価計算は、一見複雑ですが、実はパズルのようにルールがはまると気持ちよく解けるもの。
「数字が苦手」でも、ルールを理解して練習すれば克服できます。
大切なのは、「なぜそうなるのか」という論理的な流れを追うことです。
簿記3級を経て挑戦すると有利になる理由と、2級から始める際の注意点
3級からのステップアップなら、基本の仕訳や財務諸表の知識が土台になるので有利です。
ただし、2級から直接挑戦する人もいます。
その場合は基礎の補強に時間を割く必要があるので、3級レベルの教材をざっと復習してから入るのがおすすめです。
最重要!インプットよりアウトプット(過去問演習の「質と量」)
簿記2級は範囲が広いため、テキストを読み込むだけでは不十分です。
過去問・問題演習を繰り返し解くことが合格の決め手になります。
特に連結会計や工業簿記は、問題演習で“手を動かす”ことが理解の近道になります。
過去問・問題演習を繰り返し解くことが合格の決め手になります。
特に連結会計や工業簿記は、問題演習で“手を動かす”ことが理解の近道になります。(→この「手を動かす」勉強を挫折せずに続ける科学的な秘訣もチェック!)
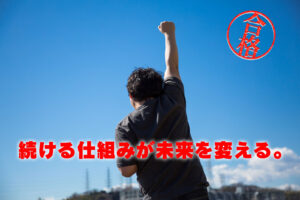
商業簿記と工業簿記を並行して学習する「理想の比率」
「商業簿記に偏って勉強してしまった…」という声はよく聞かれます。
理想は商業簿記7割:工業簿記3割のペースで、バランスよく進めることです。
工業簿記は慣れるまで時間がかかるので、早めに取り組むのがポイントです。
苦手分野(連結・工簿)を克服する「3つのステップ」
難化要因となった連結会計や工業簿記も、以下の流れを繰り返すことで攻略可能です。
- 基本問題でパターンを徹底的に理解する。
- 過去問で応用パターンや出題傾向を確認する。
- 特に点数が取れなかった苦手部分だけをピックアップして繰り返し解く。
👉 これらの独学対策を続けてもなお、難解な連結会計や工業簿記でつまずきそうであれば、プロのカリキュラムに頼るのが賢明です。最短で合格したい方は、以下をチェックしてみてください。
✅ 今から準備を始めて、着実に合格を目指しましょう。
独学に不安があるなら通信講座の活用もおすすめ
独学でも合格は可能ですが、簿記2級が難しくなった今、通信講座を活用するのは非常に有効な選択肢です。
独学でも合格は可能ですが、簿記2級が難しくなった今、通信講座を活用するのは非常に有効な選択肢です。
(→【科学的根拠】挫折しないための勉強法と、それを実現するスタディングの強み)
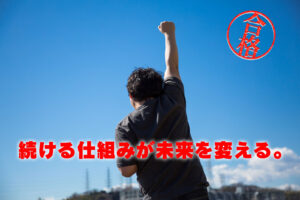
独学のデメリット(範囲の広さ・疑問解決の難しさ)
独学には、次のようなデメリットがあります。
- 範囲が広すぎて効率的に学べない。
- 難解な論点でつまずいた時に質問できない。
- モチベーション維持が難しい。
通信講座のメリット(効率化・スキマ時間学習・質問サポート)
通信講座は、これらのデメリットを解消できます。
- 出題傾向に絞った効率的なカリキュラム。
- スマホで学べるためスキマ時間を有効活用できる。
- 講師への質問や学習サポートが受けられる。
コスパ重視ならスタディングの簿記講座
スタディングはスマホ完結型で低価格なのが魅力。社会人や学生でも「通勤中・家事の合間に学べる」点が強みで、忙しい方でも無理なく学習を続けられます。
まとめ|簿記2級は難しくなったが工夫次第で合格できる
簿記2級は確かに「難しくなった」資格です。
特に連結会計や工業簿記の必須化、実務寄りの論点追加は、受験生にとって負担増となっています。
しかし、過去問演習を中心に効率的に学習すれば、独学でも十分に合格可能です。
難しくなったからこそ、合格すれば「努力できる人材」として高く評価される資格でもあります。
少しでも効率よく学びたい方は、通信講座の利用も検討してください。
特にスタディングはスキマ時間を活かした学習法に強みがあり、忙しい社会人や学生の味方です。
✅ 今から準備を始めて、着実に合格を目指しましょう。