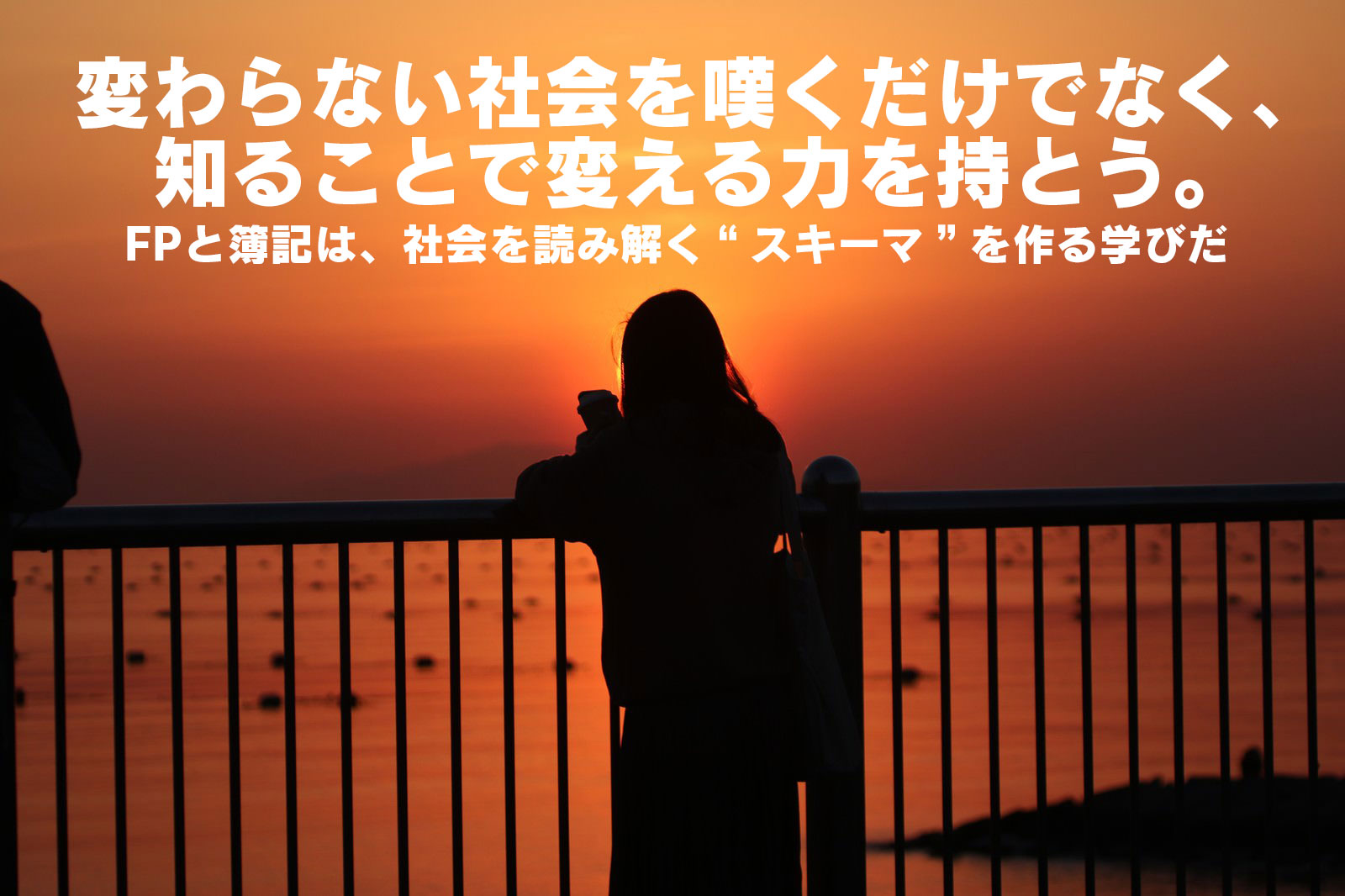変わらない社会を嘆くだけではなく、知ることで変える力を持とう。
FPと簿記は、社会を読み解く“スキーマ”を作る学びだ。
知らないことは、覚えられない。
学ぶことで、流される側から選び、動かす側へ変わることができる。
ニュースでは「賃上げ」「景気回復」という言葉が踊ります。
選挙でも政治家たちは「給料を上げる」「物価高に負けない賃金を」と訴えています。
でも、「給料が上がった」と実感できていますか?
物価は上がっているのに、手取りは増えない——そんな違和感を抱えていませんか?
実質賃金(物価を考慮した手取り)も、可処分所得(税や社会保険料を引いた実際に使えるお金)も、上がるどころか減っている現実。
その理由は、経済と政治の仕組みを学べば見えてきます。
学びは無力じゃない。
知ることが、変える第一歩なのです。
1. 日本の給料が上がらない構造的理由
日本で給料が上がらないのは、単なる「景気の悪さ」や「企業努力不足」だけではありません。
背景には、税制や法律、そして労働市場を取り巻く構造的な問題が潜んでいます。
1-1 消費税の仕組みが賃上げを阻む
消費税は、私たち消費者だけでなく、企業にとっても負担です。
例えば、企業が派遣会社に支払う派遣費用には消費税がかかりますが、これは仕入税額控除で取り戻せます。
一方で、正社員の給与には消費税がかからないため、控除対象になりません。
※給与は「仕入れ」ではないため、企業はその分の消費税を取り戻せないのです。
つまり、企業にとっては
✅ 派遣社員を使う方が税制上有利
という歪んだインセンティブが生まれてしまうのです。
もし消費税を廃止すれば、
✅ 企業のコスト負担が軽くなり、賃上げ余力が生まれる
✅ 派遣優遇の税制インセンティブが消えるため、正社員雇用が増える
✅ 消費税分が商品価格から消えるため、物価が下がり実質賃金が上がる
1-2 派遣法改正で低賃金競争が加速
2000年代、小泉政権下で派遣法が改正され、製造業派遣が解禁されました。
この結果、
✅ 派遣社員が急増
✅ 正社員比率が低下
✅ 平均賃金が下がる
という現象が起きました。
確かに、製造業派遣には「景気や需要の波に合わせて雇用調整できる」というメリットもあります。
しかし、結果的には低賃金競争が常態化し、労働市場全体の賃金水準を押し下げたのです。
もし派遣法を改正前の「専門業務派遣限定」に戻せば、
✅ 派遣に頼れなくなった企業は正社員化を進める
✅ 雇用が安定し、賃金も底上げされる
という変化が期待できます。
1-3 外国人労働者受け入れと賃金停滞
さらに、外国人労働者の受け入れ拡大も賃金停滞の一因です。
- 特定技能:労働力不足解消が目的
- 技能実習:人材育成が建前(実態は低賃金労働力供給)
制度の目的と実態に乖離があることが、結果的に低賃金構造を固定化している可能性があります。
安価な外国人労働力が増えれば、企業は無理に賃金を上げる必要がなくなります。
結果として、国内労働市場全体の賃金上昇圧力が抑えられてしまうのです。
2. 日本の政治と経済政策は誰のため?
ここまで見てきたように、税制や雇用政策には、表向きの目的と裏腹に賃金上昇を妨げる側面があります。
では、こうした政策で誰が得をしているのでしょうか?
✅ 外国人労働者受け入れ拡大 vs 賃金上昇
✅ 派遣規制緩和 vs 雇用安定
✅ 消費税維持 vs 可処分所得増
- 大企業は安い労働力を確保できる
- 政権与党は大企業からの献金や支持を維持できる
結果的に、恩恵を受けているのは一部の大企業や既得権益層であり、私たち生活者にはその果実が届きにくい構造になっているのかもしれません。
3. 構造変革がもたらす光と影
もし
✅ 消費税を廃止し
✅ 派遣法を改正前に戻し
✅ 外国人労働力受け入れを厳格化したら
社会はどう変わるでしょうか。
💡 【予想される変化】
- 派遣優遇の税制インセンティブが消える
- 企業は正社員雇用に切り替えざるを得なくなる
- 労働市場がひっ迫し、賃金が上がる
- 消費税廃止で物価が下がり、可処分所得も増える
ただし、副作用もあります。
✅ 派遣労働や外国人労働力に依存してきた業界で人手不足が深刻化
✅ 企業は機械化・AI化で対応しようとし、短期的には雇用が減る可能性
この副作用は、市場全体の構造変化として波及してしまいます。
- 企業が潰れれば、雇用が失われ、地域経済が冷え込む
- サービスが減れば、消費者の選択肢が狭まり、生活の質が下がる
- 結果として、**「困るのは結局、私たち」**という構図になりがちです。
だからこそ、“どんな未来を選ぶか”を一人ひとりが考える必要があるのです。
4. 私たちができること|社会を変える現実的アクション
ここまで、給料が上がらない構造の原因と、それを打開する政策案を見てきました。
では、一市民の私たちは何ができるのでしょうか。
✅ 選挙で民意を示す
選挙は直接的な政権交代をもたらすだけでなく、民意を示すことで政策変更や与党内改革を促す重要な手段です。
※ 参議院選挙は政権選択選挙ではないものの、与党が大敗すれば首相退陣や衆院解散総選挙に繋がる場合もあります。(例:2007年参院選大敗 → 安倍第一次政権退陣)
✅ SNSやブログで声を届ける
日々の疑問や気づきを発信することで、同じ問題意識を持つ人とつながり、世論形成の一助になります。
✅ 与党内の改革派や刷新派を応援する
社会を変えるのは野党だけではありません。与党内の改革派が力を持てば、政策も変わっていきます。
✅ 地方から国を動かす
地域での選択や投票行動が、全国的な潮流を生み出すこともあります。
そして何より大切なのが、
✅ **「学びによって意識を変えること」**です。
5. FP・簿記で“スキーマ”をつくる
知らないことは、覚えられない。これは学習の大原則です。
ニュースや政策、政治家の言葉も、頭の中に“スキーマ”(認知の枠組み)がないと理解されず、流れていってしまいます。
✅ FP(ファイナンシャル・プランナー) を学べば、
税金・社会保障・投資など生活に直結する制度が見えてくる
✅ 簿記 を学べば、企業の会計やお金の流れの裏側を読み取れるようになる
つまり、FPと簿記は、社会の裏側に届くレンズを持つ**“市民の武器”**になるのです。
【まとめ】
ただ嘆くのではなく、問い、学び、動く。
その連鎖こそが、社会を静かに、でも確実に変えていきます。
“知らない”ことで奪われてきた未来を、
“学ぶ”ことで取り戻そう。
FPや簿記は、あなたのリテラシーと人生を照らす最初の一歩です。
Q&A
- 「制度のせいにしすぎじゃない?企業努力の問題では?」
-
企業の努力ももちろん重要です。ただし、消費税や派遣法のような制度が“正社員より派遣を使う方が得”という歪んだインセンティブを作っている現実があります。構造が行動を縛っている以上、制度に目を向けなければ本質的な解決はできません。
- 「外国人労働者を制限したら、介護や農業が回らなくなるのでは?」
-
問題は“受け入れそのもの”ではなく、“安価な労働力としての依存”にあります。制度の目的と実態が乖離したままでは、低賃金構造が固定化され、結果的に誰の賃金も上がらないという負の連鎖が続きます。大事なのは“どう受け入れるか”を考えることです。
- 「消費税廃止なんて非現実的では?」
-
完全な廃止だけが選択肢ではありません。軽減税率の拡充や段階的な減税、代替財源(資産課税の見直しなど)の検討も含め、「消費税が本当に最適な財源なのか?」を再設計する議論こそが求められています。
- 「FPや簿記の学びって誰でもできるの?」
-
全員が一気に資格取得を目指す必要はありません。ここで伝えたいのは、“学ぶことで社会と制度の仕組みが見えてくる”ということ。最初はYouTubeや書籍でも構いません。「自分の生活と社会はつながっている」と気づくことが、意識変革の一歩になります。
- 「結局、何をすればいいの?」
-
文句を言うだけでなく、「問いを立て、学び、読み解き、動く」こと。それが社会を静かに、でも確かに変えていく力になります。FPや簿記はそのための“市民の武器”。学びは、未来を選ぶ力そのものです。